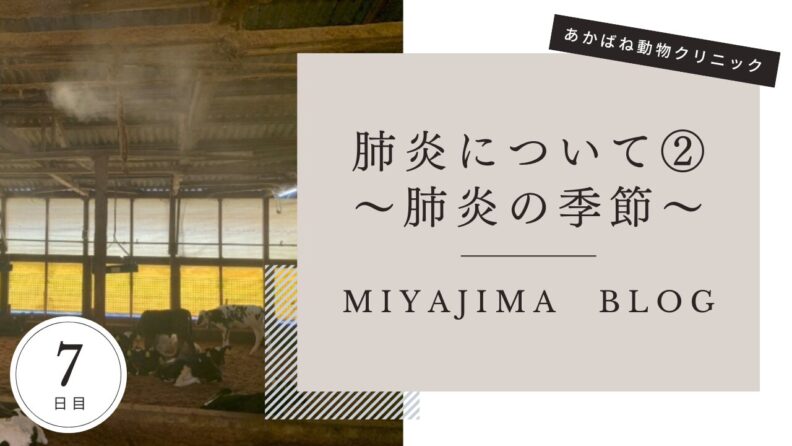エサを喰わせる哺育管理
うちの哺乳は、朝夕で3Lずつ、1日6L給与しています。哺乳に力を入れている農家さんに比べると少ないと思います。それに加え、離乳までの期間は減乳法で、離乳前には朝夕1Lずつの1日2Lまで落とします。
そうです。うちはミルクを飲ませることよりも、エサを食べさせることがメインになります。子牛達を育てる「育成」と言うよりは、「つくる」という意識で管理しています。あくまで私の感覚ですが、「育成」は祈る、願う、などの要素が含まれているように感じます。それに対して「つくる」は、実行、実現だと感じるので「つくる」を意識しています。
子牛への手厚い取り組み
その作ると言う意識のなかで、子牛達をより良く管理するために、胃腸作りに欠かせない「微生物」に力を入れています。
哺乳をしている段階では、とくに小腸の働きが重要だと感じているので、小腸に効果的な微生物製品をミルクに混ぜて給与しています。スターターを食べ始めた段階で、ルーメン、大腸に効果的な微生物製品をスターターと一緒に給与しています。
もう一つの取り組みとして、ルーメン液移植も行なっています。早い段階から胃腸を作ることで、計画通りに、スムーズに子牛ルーメンを作ることができると考えています。
うちでは、大きくするのは縦の体高ではなく、横の幅で、丸くすること意識しています。ですので、実はスターターから切り替える配合飼料は、育成配合ではなく、エネルギーの高い搾乳牛用配合を給与しています。全ステージ、同じ配合にすることで、切り替わるストレスを無くしています。
離乳後4カ月までは、バイパス飼料を1日100~300g給与しています。バイパスなので少量でも効果的で、個体差を見て給与しています。とくに冬は少し延長して、5カ月までは、寒冷対策や増体、皮膚や毛並みを整えることを考えて、1日200~400gを給与しています。
バイパス飼料を給与している理由は、配合の増量によるルーメンアシドーシの恐れを予防することと、バイパスでエネルギー、油脂が利用でき、少量でも高い効果があるので給与しています。給与している飼料は、ペレット状で嗜好性がとても良く、子牛達も食べやすいです。
育成の飼養環境
子牛達は、離乳するとハッチから移動します。就農当初は、そのままD型育成舎に移動していました。そのときの育成牛の管理は、個体の能力も低いこともあったとは思いますが、体型など個体差があり、良い牛群とは言えませんでした。
なので、就農2年目春〜現在までは、離乳〜3カ月齢くらいまで、搾乳牛舎に経産牛達と並べて管理しています。育成牛舎より搾乳牛舎の方が観察しやすく、離乳後の安定しない体調の管理に対応できるので、体型を揃えることができるようになりました。
ハッチの個別管理から、育成舎の群管理への移行に関しては、色々なことを考えて実践しているので、次回は今の管理を紹介します。