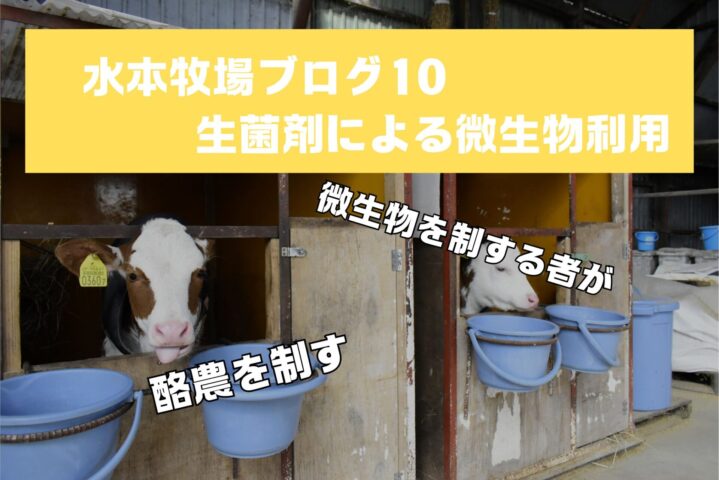Dairy Japan2025年4月号特集「哺育・育成管理の極意」より「ルポ1 北海道日高町、日高キャトルセンター」の事例
INDEX ➖
哺育・育成の「分業化」で地域酪農を守る
子牛の哺育・育成は、酪農家にとって時間も労力もかかる大変な仕事です。近年は労働力不足も深刻化し、育成まで手が回らないという声も多く聞かれます。そこで本特集では、北海道日高町で2021年に設立された、日高キャトルセンタ株式会社の取り組みを取材しました。
同センターは、地域の酪農家が子牛の哺育・育成を預けられる民間施設として運営され、現在は道内のみならず全国から約1000頭もの育成牛を受け入れています。現場ではどのような管理が行なわれているのでしょうか?

どんな牛も“健康第一”の徹底管理
日高キャトルセンターでは、子牛が到着すると、まず隔離舎で健康チェックを行ないます。体重や体高、臍(へそ)の様子、糞便・血液検査まで丁寧に確認し、安全が確認された牛のみが哺育舎へと移動します。
哺乳はミルクタクシーと乳首付きバケツで実施され、次の段階ではロボット哺乳に移行。体重・哺乳量・採食量などのデータはすべて行動管理センサーで管理され、異変があればすぐに対応できる仕組みです。増体量や採食量なども1頭ごとに把握できる仕組みが整えられています。哺育・育成牛を専門的に管理する同センターにおいて、すべての管理を重要視しつつも「やはり最重要は哺育期間」とのこと。ここで上手くいかないと、その後すべての時期でどれだけ良くしても限界があるということでした。

さらに授精前の育成前期牛まで体重測定を継続し、発情発見や授精のタイミングも、データをもとに明治飼糧株式会社の技術者と連携して進められます。
草の質にこだわった「腹作り」
同センターが大切にしているのは、「哺育期の増体がその後の成長を決める」という考え方。離乳後の育成前期では、フィードステーションによる配合飼料の給与とともに、高品質な1番草など繊維豊富な乾草を与え、“腹を作る”ことに力を入れています。

これにより、しっかりとしたルーメン(第一胃)の発達が促され、その後の採食量や健康状態に好影響を与えています。そして、ここでもやはり管理担当者が明治飼糧の担当者にこまめな連携を取り、ロスの少ない管理を実現しています。

良い草を安定して届けるために
乾草はすべて購入している同センターですが、これまでは品質のばらつきが課題でした。そこで場長の日下正昭さんを中心に、道北のTMRセンターと直接やり取りを重ね、日高キャトルセンター専用の高品質な牧草供給体制を確立。現在では草の質が安定し、育成にも好影響をもたらしています。
「牧草でも牛でも、信頼関係があってこそ。顔が見える取引が大事」と語る日下さんの言葉からも、丁寧な仕事ぶりが伝わります。

作業の標準化で働きやすさも実現
少人数で多くの牛を管理するため、同センターでは作業の平準化にも力を入れています。ロボット哺乳や自動給飼、舗装された作業動線などを活用し、「誰でもすぐに仕事を覚えられる」体制を整備。スタッフが余裕をもって働ける環境作りが、牛への丁寧な管理にもつながっています。

信頼と仕組みが、良い子牛を育てる
日高キャトルセンターの取り組みから見えるのは、「データに基づいた管理」と「人との信頼関係」の大切さです。効率を追うだけでなく、1頭1頭の状態にしっかりと目を向けた育成が、健康な乳牛を育てる土台になることがわかりました。
PROFILE/ 筆者プロフィール

前田 真之介Shinnosuke Maeda
Dairy Japan編集部・北海道駐在。北海道内の魅力的な人・場所・牛・取り組みを求めて取材し、皆さんが前向きになれる情報共有をするべく活動しています。
取材の道中に美味しいアイスと絶景を探すのが好きです。
趣味はものづくりと外遊び。