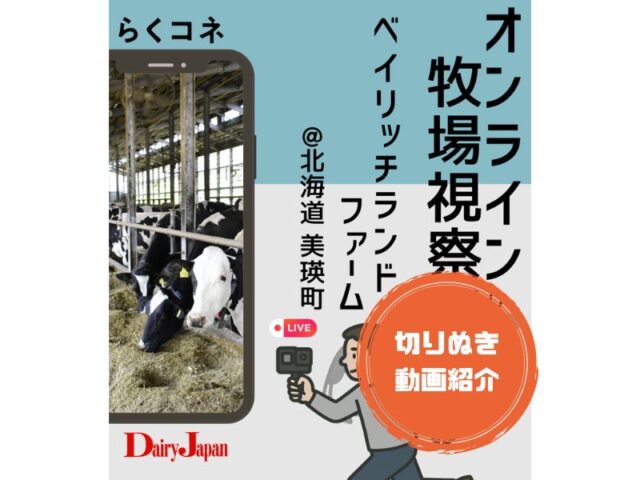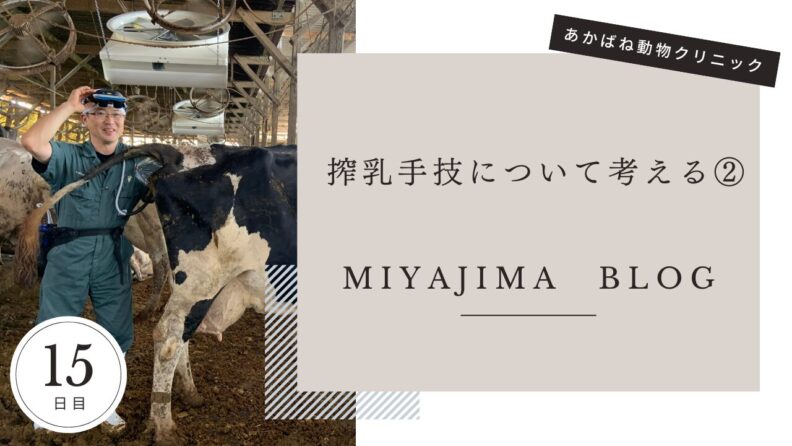『Dairy Japan 2024年12月号』P.24「初産分娩までが未来の経営を左右する No.10=育成牛の栄養要求と給飼=」より
育成牛は、あなたの農場の将来の牛群です。ですから育成管理の改善は、経営基盤の強化と言えます。
育成管理の改善に軸足を置いた「初産分娩までが未来の経営を左右する」と題したシリーズで、海田佳宏さん(株式会社 清流酪農サービス・代表)が詳しく解説してくださいました。
今回は、その10回目です。以下、抜粋・要約。
日本飼養標準と育成牛の栄養要求
『日本飼養標準 乳牛2017年版』(以下『日本飼養標準』)では、育成牛の受胎までの栄養要求はステージによって異なり、CPは16~12%、TDNで72~63%となっています。受胎以降の蛋白要求は12%、TDNは60から51%とされています。飼料中のCP含量が低いと飼料の消化率が低下する傾向にあるため、12%以上確保することが推奨されています。また、高い増体を確保するためには受胎前の蛋白は15%以上必要としています。
受胎時の体重が大きいと初産乳量が高い傾向がある一方、過度の増体(日増体1.03kg以上)は乳量が低下することが示唆されています。
NASEMと育成牛の栄養要求
『NASEM乳牛栄養要求 第8版』(以下『NASEM』)では、ステージ別の育成栄養ガイドラインのうち増体分の組成に注目すると、生体重112kgでは11%が脂肪、16%が蛋白になっています。生体重560kgでは脂肪が31%、蛋白が12%となり、増体の組成に大きな違いが見られます。
エネルギーと蛋白の要求は「MP/ME」が示されていて、MPは蛋白、MEはエネルギー要求量を意味しています。「MP/ME」が大きいと蛋白の要求が高く、小さいとエネルギーの要求が高くなります。若齢の育成牛は骨格形成時期なので、蛋白の要求が高いのです。
分離給与とTMR
『日本飼養標準』も『NASEM』も育成牛の栄養要求量を詳細に提示していますが、現場段階では、これらの要求を、どのように満たしていくのか、が課題になります。給飼方法を採択し、栄養のバランスを整え、育成牛に食べさせる方法は農場により異なります。
育成牛への給飼方法は、「分離給与」と「TMR」に大別されます。TMRにトップドレスとして濃厚飼料や粗飼料給与を組み合わせる方法もあるので、さまざまな給与方法が存在します。グループ分けの方法や施設によって採用される給飼方法もあり、たくさんの組み合わせが選択可能です。
どのような給与方法でも、十分な飼槽スペースが必要です。ただし、分離給与しない場合のTMR給与は、やや制限された飼槽スペースも許容されます。これはTMRが濃厚飼料も含んだ構成なので、飼槽にアクセスできたらバランスの取れた栄養摂取が可能であるためです。配合飼料を個別給与する場合は、全頭整列可能な飼槽幅が必要です。
分離給与の場合は、濃厚飼料と粗飼料(乾草、サイレージ、放牧草など)の給与となります。適正給与の基準は「足し算」や「引き算」が基本となります。例えば、低品質な粗飼料が給与されている場合やストレス下では濃厚飼料を増給し、過肥の傾向にある場合は逆に減量します。これらの給与量の調整は、発育やBCSのモニタリング結果に基づき調整するのが良いでしょう。
TMRを給与する場合は「掛け算」や「割り算」で給与調整を行ないます。グループに在籍するステージや頭数に基づき栄養設計を行ないます。また、育成牛に搾乳牛のTMRを給与する場合がありますが、カロリーオーバーにならないように粗飼料を併給するなど工夫してください。育成用のTMRを給与する場合は、ベースとなるTMRに濃厚飼料をトップドレスすることで複数のグループに適応することができます。多頭飼育の場合は、グループ単独のTMR給与になるでしょう。どの給与方法でも、必ず1頭当たりの給与量を算出して栄養充足の検証を行ないましょう。
本稿(Dairy Japan 2024年12月号)では、「育成牛の体重別での栄養要求量(表)」や「妊娠の要求」「分離給与とTMRの飼料計算例」「育成牛への制限給与」など、より詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。
PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa
DairyJapan編集部。
1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。
趣味はサッカー観戦。
取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。
皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。