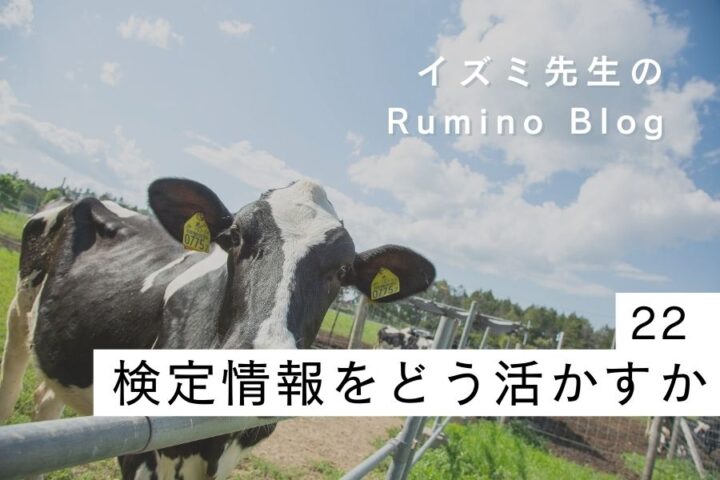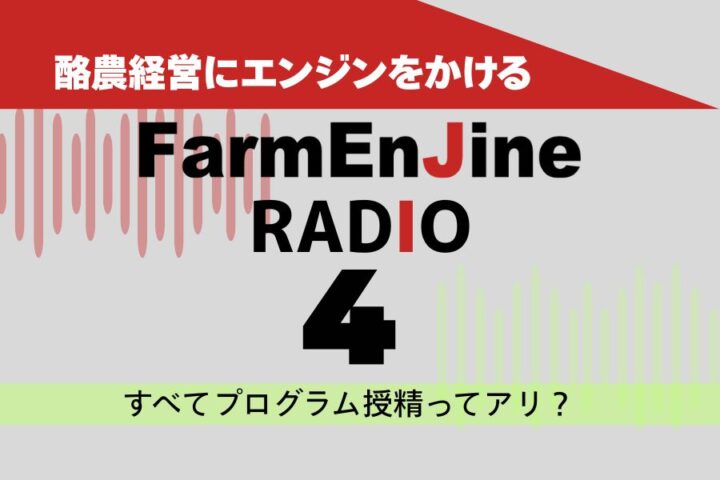秋が近づいてきました。北海道では、スラリーや堆肥の散布がそろそろ本格化してくる頃です。
今回は「施肥設計に、スラリーや堆肥って含めていますか?」という問いかけから始めてみようと思います。
この記事は、
- 肥料代をなるべく減らしたい
- 土や肥料にちょっと興味がある
そんな酪農家さん向けに書いています。
スラリーや堆肥も「設計の一部」です
肥料の設計って、ざっくり言えば「何を、どれくらい入れるか」を決めることですよね。でも、その設計に「スラリーや堆肥」が含まれているか? と聞かれると……実際のところ、抜けていることも多いんじゃないでしょうか。
スラリーや堆肥にも、ちゃんと窒素、リン酸、カリウム、ミネラルが含まれています。言ってしまえば、すでに持っている肥料です。
施肥設計の3ステップ(とてもシンプル)
設計を考えるとき、僕はいつもこの三つで整理しています。
- どんな畑にしたい?(ゴール)
- 今どこにいる?(現状)
- 何をしていく?(方法)
これは当たり前の話で、施肥設計だけじゃなくて、経営や人生にも当てはまると思っています。ナビと一緒ですね。行き先を決めて、現在地を知って、ルートを決める。
1. どんな畑にしたい?
「去年よりも草を多くとりたい」とか、シンプルに「草の質を上げたい」でも十分です。自分の経営に合った目標を、まず最初に思い描きましょう。
ここが曖昧だと、「なんとなく去年と同じ」になって、改善のしようがありません。
2. 今の状態を知るには?
目標が決まったら、次は「今どうなっているか」を見ていきます。
- 土壌分析(体感も大事です)
- 昨年使った化学肥料の量と成分
- 収量や草の質(成分)
- スラリーや堆肥の分析結果
ここまで揃うと、かなり設計に落とし込みやすくなります。
ちなみに、酪農だと「乳検データ」や「エサの設計」も実は関わってくるので、経営全体で見ていく視点も必要になりますね。
3. じゃあ、何をしていく?
目標と現状がわかったら、ようやく方法を考える番です。
例えば……
- 肥料を増やす?減らす?
- 土のpHを整えるためにカルシウムを入れる?
- 過剰気味なカリを抑える?
ここでやっと、肥料を「足す・引く」判断ができるわけです。
スラリーや堆肥、分析してますか?
僕の実感では、スラリーや堆肥を成分分析している酪農家さんは、まだ少ないです。でも実際には、アンモニア態窒素や硝酸態窒素を「窒素」に換算できますし、リン・カリも同様です。
つまり、化学肥料を減らす根拠になるんです。
とくに「カリ」は過剰気味なケースが非常に多いので、スラリーや堆肥の中身を見直すだけで「もうカリは要らない」って結論になることも珍しくありません。
感覚も、大事。でも言語化しよう。
施肥設計は、数字だけじゃなくて感覚も大切だと思っています。でも、その感覚を言葉にしておくことで、次につながります。
例えば……
- 「土が柔らかい=菌が多い。だから肥料は控えよう」
- 「カチカチで乾燥気味。数値上は肥料が足りないけど、堆肥を倍入れてみる」
こんな感じでいいんです。
体感を含めた判断も、振り返れるように言語化しておくと、設計の一部として残せます。
最後に:皆さんの感覚は、正しいです
個人的な意見ですが、酪農家さんの感覚って、ほとんどズレていません。現場で毎日見て触れているからこそ、信じられるものがあるんだと思っています。
だからこそ、その感覚に分析をちょっと足すだけで、さらに強い施肥設計ができる。
秋の散布前に、一度だけでも、スラリーや堆肥の分析やってみてはいかがでしょう?
PROFILE/ 筆者プロフィール
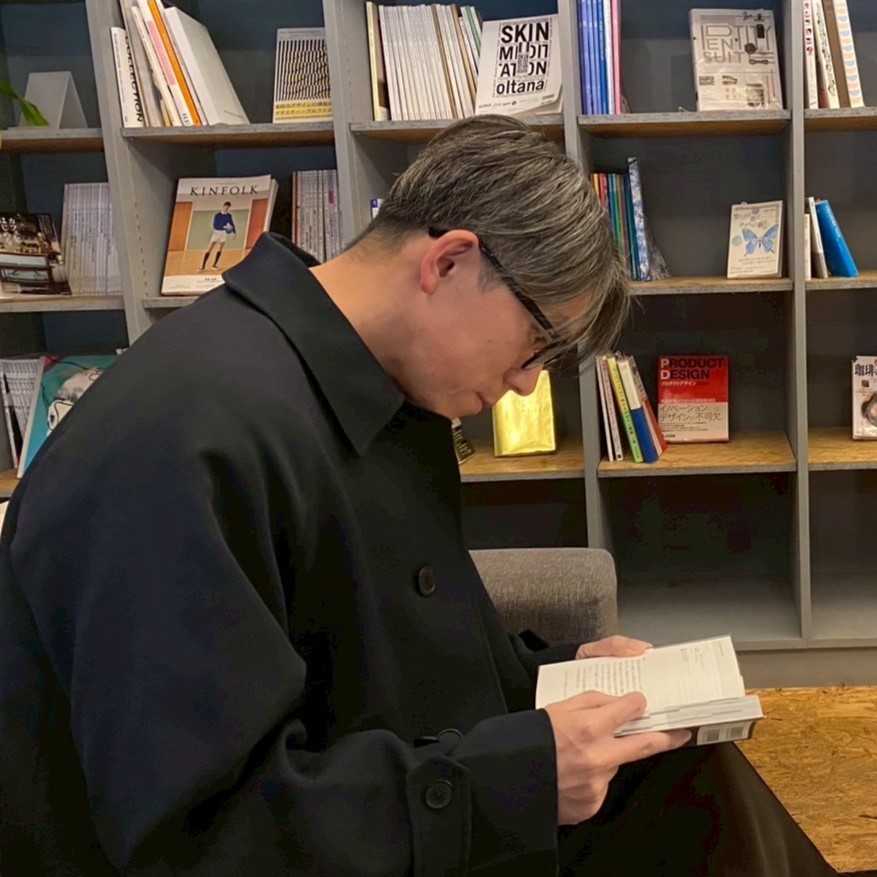
今村 太一Imamura Taichi
標茶町を拠点に、土壌改良資材の販売や周辺酪農家さんのサポートをする「soil」の代表。飼料会社に13年勤めた後、ドライフラワーやマツエク、ネイルのお店を経営。弟と一緒にsoilを立ち上げ、今は土や牛、人とのつながりを大事にしながら活動中。
経営やコーチング、微生物の話が好きです。「目の前の人に丁寧に」が大切にしている想いです。