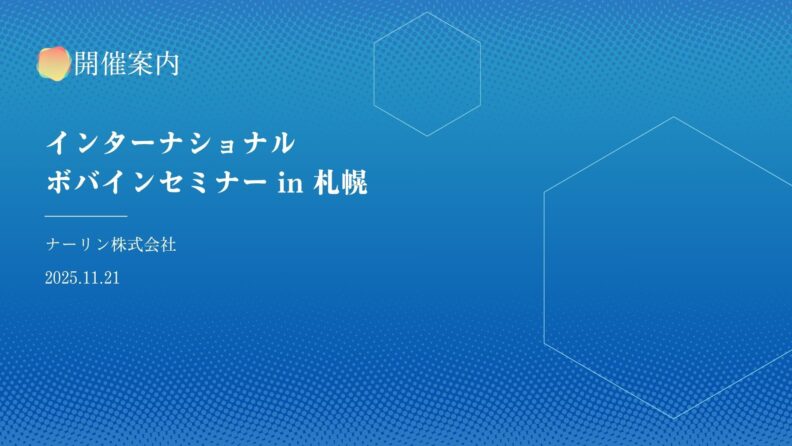突然ですが、わが家にはメンコイ愛犬が2匹います。小型犬のミカンちゃんと盲導犬候補生だったナルちゃんです。ここに、新たに盲導犬候補生の子犬がまもなく加わります。北海道盲導犬協会から、生後数カ月の盲導犬候補のラブラドール犬を1年間預かるパピーウォーカーというボランティアになります。この子犬にはDを頭文字とする名前をつけることになっており、家族で楽しみながら悩んでいるところです。
さて、わが愛しのワンコ達は、「トイレ」「待て」「座れ」「伏せ」など最低限の行動は身につけています。これらの行動を身につけさせるために、おやつを与えて褒めて教え込んでいきました。おやつのように嗜好性の高いエサを用いて、動物にこちらの望む行動を引き起こすための刺激を正の強化子と呼びます。成功したときにはグッドというかけ声や、クリッカーという器具を使ってカチッと音を鳴らすことで、行動をすると報酬をもらえることを学ばせていきます。専門的にはこのようなトレーニングをハズバンダリートレーニングと呼びます(川瀬と椎原, 2018)。動物園で飼育されている動物では、ハズバンダリートレーニングが成功すると、じっと静止して採血をさせてくれるようになるそうです。牛に近いところではキリンも訓練をしており、いくつかの測定をさせてくれるようになるそうです。

写真は「座れ」と「待て」の訓練中です。
先日、アルバータ大学の大場教授を本学にお招きして、私が担当する乳用家畜飼養学実習で特別講義をお願いしました。そのときの質問タイムで、履修学生が面白い質問をしました。それは「子牛も犬や猫のようにしつけをすることができると思いますか?」という内容でした。われわれ乳牛栄養学を専門とする者にとっては想定外の質問でしたので、明確に回答することはできませんでした。ですが、牛は哺乳や給飼、搾乳などの時間を覚えますので、ひょっとしたら可能かもしれません。かといって、犬のように「座れ」や「お手」を教えるのは意味がないように思います。それでは、採血はどうでしょうか。牛の採血はモクシやスタンチョンで保定して行なうのが一般的です。身動きできないように行動を制御して行なうわけですが、おやつとクリッカーによって保定せずに採血できるようになるかもしれません。ハズバンダリートレーニングを用いた乳牛の行動コントロール、ちょっと面白そうに思います。卒論でやってみようかな??
PROFILE/ 筆者プロフィール

泉 賢一Kenichi Izumi
1971年、札幌市のラーメン屋に産まれる。1浪の末、北大に入学。畜産学科で草から畜産物を生産する反芻動物のロマンに魅了される。修士修了後、十勝の酪農家で1年間実習し、酪農学園大学附属農場助手として採用される。ルミノロジー研究室の指導教員として学生教育と研究に取り組むかたわらで、酪農大牛群の栄養管理に携わる。2025年4月、27年間努めた酪農大を退職し、日本大学生物資源科学部に転職する。現在はアグリサイエンス学科畜産学研究室の教授。専門はルーメンを健康にする飼養管理。最近ハマっていることは料理と美しい弁当を作ること。