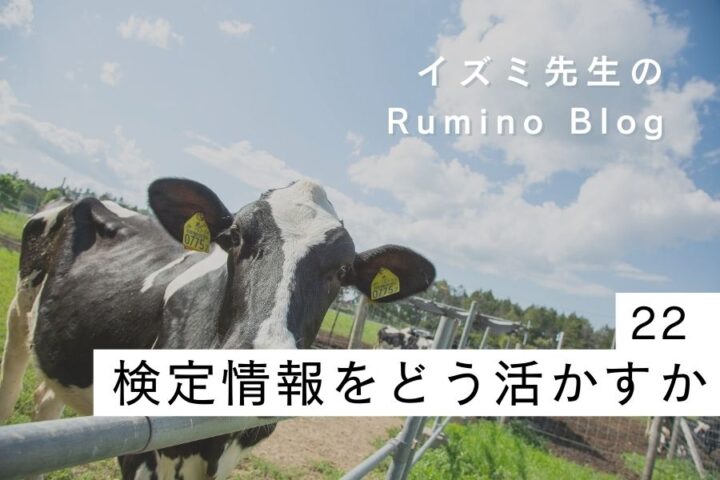こんにちは! 遅くなりましたが、FarmEnJineラジオ6回目の公開です!
今回は小林悟さんに「離乳以降期に最適な粗飼料体制」についてお話を伺ってきました。
以下に簡単なまとめを記載します。
なぜ「哺育期から少量粗飼料」なのか
哺乳量やスターター摂取を阻害しない“少量”の粗飼料を哺育期から与える狙い。
- ルーメン内の滞留物を“流す”効果:繊維が第一胃内容の流動性を助ける。
- ルーメンpHの干渉(緩衝)効果:pH低下期のリスク緩和。
- 異常行動の抑制:元気な子ほど敷料など余計なものを食べがち→可食の繊維源で置き換える。
ポイントは“量と質”。「喰わせれば良い」ではなく、「哺乳・スターターを邪魔しない量で、食べやすい繊維」を選ぶ。
何を与えるか:現場で“食う”ものが最優先
時給ロール(自家ロール)を試しても“ちゃんと食う”例が意外に少ないケースがある。小林さんの経験的には、輸入オーツ(オート麦乾草)が安定して嗜好性が高く、切断長も短くて食べやすい。
- 嗜好性:糖分が効いて“まず食う”。
- 物性:柔らかく、シャクシャクとほぐれる。
- オーツは30時間消化率:50%後半〜60%超のものもあり、使いやすい。
- コスト感:1kgも食べない前提なら、70円/kg台でも十分“元が取れる”。
一方、クレインはロット差が大きい。硬いロットは見送り、良ロットが確保できるときのみ選択肢に。
さらに、ラップサイレージは水分多くて少頭数の牧場では使い切る前に悪くなることもあるけど、オーツは乾燥してるから1週間かけて使っても痛みづらい。
など、ロールの重要ポイントは「ちゃんと食ってくれること」ですね。成分が良くても食わない時がある。嗜好性が最優先。
続きは動画でご覧ください!
PROFILE/ 筆者プロフィール

大塚 優磨Otsuka Yuma
株式会社FarmEnJine代表。
「酪農業界にエンジンをかける」をモットーに、栄養・繁殖それぞれの専門的視点での酪農経営の課題の洗い出しや、酪農経営のゴール設定、など、「本当に酪農家を豊かにする」ためのサポートを行なう。
スタートアップの企業につき、Youtubeで酪農に役立つ情報を公開中