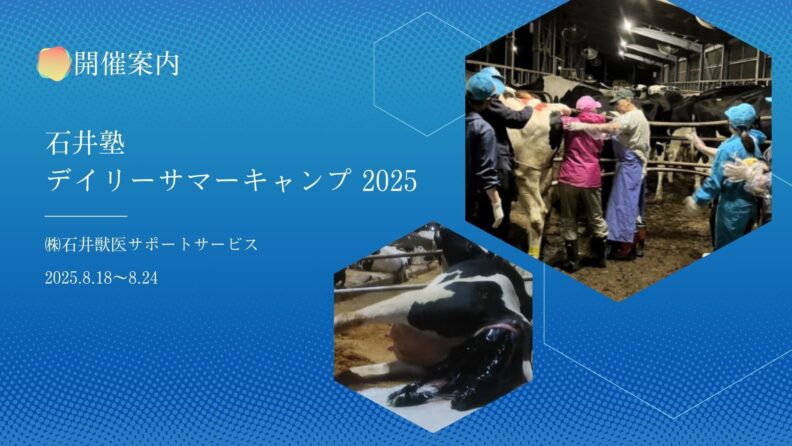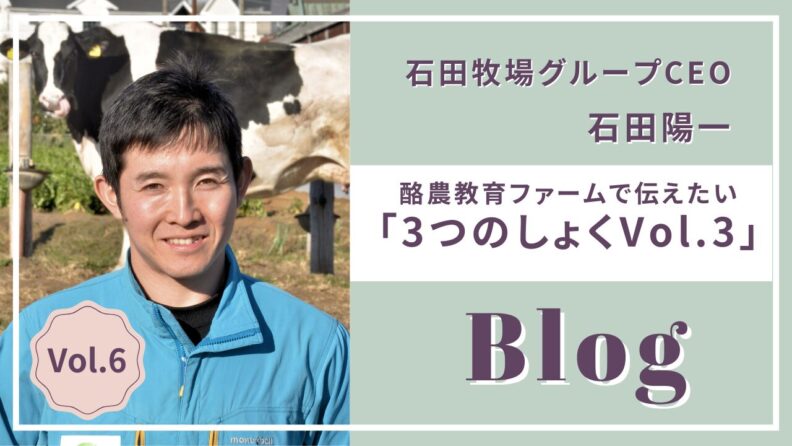『Dairy Japan 2024年9月号』P.23「初産分娩までが未来の経営を左右する No.7=環境要因の対策=」より
育成牛は、あなたの農場の将来の牛群です。ですから育成管理の改善は、経営基盤の強化と言えます。
育成管理の改善に軸足を置いた「初産分娩までが未来の経営を左右する」と題したシリーズで、海田佳宏さん(株式会社 清流酪農サービス・代表)が詳しく解説してくださいました。
今回は、その7回目です。以下、抜粋・要約。
栄養面と施設面に分けて考える
環境要因が育成牛の発育に影響するのであれば、健全な発育を達成するために対策を講じる必要があります。現場で、どのような対策を検討したら良いのでしょうか?
それは、「栄養面」と「施設面」に分けて考えるのが効果的です。
施設面の改良は、「熱の伝わり方」を検証し、複数の対策を組み合わせると効果的です。夏期と冬期とでは、まったく異なる対策が必要です。
具体的な改善は、農場の実情に即した対策が好ましいので、「現場観察力」が問われるでしょう。
栄養管理と環境要因=暑熱期=
暑熱期は維持要求量が増加する一方で、採食量が低下する点にあります。濃厚飼料に比べ粗飼料は消化の過程で代謝熱発生量が多く、暑熱時の採食量が低下する傾向にあります。
夏期間は、飲水の要求が高まるので十分に給水します。また、授精ステージの牛達は暑熱期の栄養不足で種付けが遅延することもあり、注意深く対策を検討したいステージです。
栄養管理と環境要因=寒冷期=
中長期的な寒冷状況下では、牛は熱量を確保するため、採食量を増やして環境に適合しようとします。このときに維持要求量も増加するので、給与する飼料エネルギーを増給する必要があります。
このような状況下では、配合飼料の増給や、高栄養の粗飼料を給与することになるでしょう。
本格的な寒気が到来してから飼料を増給するよりは、数週間前から寒冷期用の飼料に切り替えていくことで、速やかな移行が達成されるでしょう。
温度コントロールの基本
環境温度を制御するためには、「熱の伝わり方」の理解が土台になります。
1 対流、2 伝導、3 輻射、4 蒸散、の4種類があります。
1 対流:熱が空気により移動して運ばれる現象のことです。この熱の伝わり方と同じ方式は、エアコン、温風ヒーターを想像してもらえたら良いでしょう。暑熱対策としては、十分な換気と送風です。寒冷時は、隙間風を防ぐことや、子牛にジャケットを装着することなどが代表的な対策です。
2 伝導:温かい物や冷たい物に接触することで生じる熱の伝わり方です。例としては、カイロや水まくらです。寒冷期に、敷料の少ないコンクリートの牛床に横臥している牛を想像してください。床からの冷気でお腹を冷やし、寒冷ストレスを受けるので、敷料の多用や断熱効果のある素材を設置することが効果的な対策です。
3 輻射:熱源により加温あるいは冷却された空気が対流して感じる熱を示します。例としては、赤外線ヒーターや太陽光です。屋根への断熱材施工は、輻射熱対策として有効です。酷暑下では、太陽光(輻射熱)で温められた空気が対流熱として暑熱を助長します。寒冷期は、雪・氷・冷気の輻射熱で空気が冷却され、強烈な寒気をもたらします。この輻射熱への対応は対流熱を制御することになるので重要な環境対策です。牛は暑熱時に輻射熱を避けるため日陰を求め、寒冷期は逆に日向を好みます。これらの要求を満たしてあげることが対策の基本になるでしょう。
4 蒸散:水分が水蒸気になって外に発散することを蒸散と言い、その際に奪う熱を気化熱と呼んでいます。高温時に牛体へ散水するのは、伝導熱により牛を冷やすのと、気化熱により熱を奪うことで暑熱ストレスを緩和しています。牛体が汚れている場合は、気化熱が発生することで低温ストレスが生じます。「低温」「被毛の汚れ」「隙間風」の組み合わせは著しく増体を阻害しますが、この気化熱によるところが大きいのです。
本稿(Dairy Japan 2024年9月号)では、「熱の伝わり方」を理解・応用した、暑熱ストレス対策や寒冷ストレス対策の現場事例が、たくさん紹介されています。
PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa
DairyJapan編集部。
1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。
趣味はサッカー観戦。
取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。
皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。