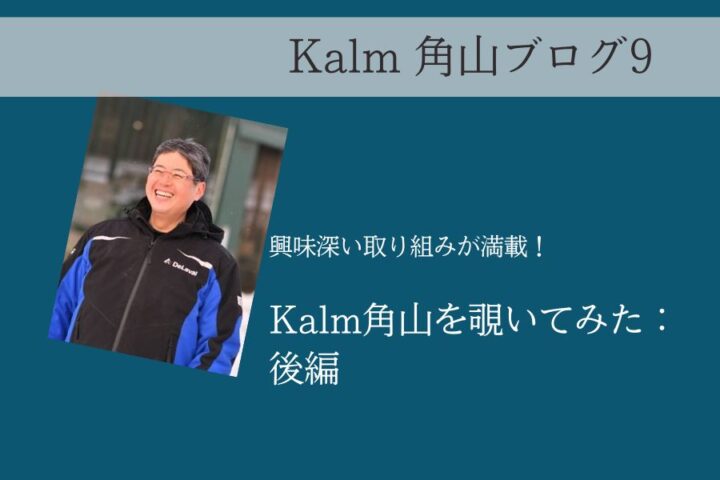Dairy Japan2024年9月号では「経営効率改善への取り組み」というテーマで取材記事を掲載しました。資材費の高騰など酪農経営を取り巻く環境は依然、厳しいものがあります。今回は、愛知県田原市のデイリーパラダイスさんの取り組みを紹介します。
INDEX ➖
●苦難のスタートが基礎に
デイリーパラダイスの社主(代表)を務める伊藤立さんは酪農家の次男として生まれましたが、実家の農場は長男が継ぐため、地元を離れて東京でサラリーマン生活を営んでいました。しかし、サラリーマン生活は「自分の頑張りが正当に評価されることは少ない」と感じ、退職したと伊藤さん。「さまざまな職業を見るなかで、販売部門が相場に左右されないのは酪農しかないのではないか」と気づき、また「自分がやっていることを隣のAさんがはじめても、自分と同じ量を出荷しても自分に損害はない。こんな職はない」と改めて酪農に強い興味を示し、父親・長男とは別の形で新規就農しました。
新規就農は第2次構造改革事業を利用して酪農団地造成に参加する形でスタート。「タイミングが悪かった」と伊藤さんは言います。それは昭和55年、生産調整によって減産の号令がかかったときだったからです。「販売数量は、すなわちお金の配分。当時の組合員も生活がかかっているから新規に枠を譲ることは難しいから難航した」と振り返り、「結果として初年度は年間6000kgの生産枠しかもらえず、悔しい思いをした。50頭ぶんの資金を集めていたが、年間6000kgでは計画が合わないわけだし」と当時の思いを話します。
●ピンチをチャンスに
「お金のことを考えると平常心ではいられない。だから朝3時から1日中、動きっぱなしだった」とがむしゃらに仕事に打ち込むことで心のバランスをとっていたと言います。しかし、当時の愛知県は暑熱ストレスへの対応も進まず、「夏に牛に構うな」という考えがあり、これが伊藤さんにとってチャンスになりました。というのは、「搾れれば、夏の増産・出荷ぶんは枠外という考え」だったから。こうして夏場に増産し、実績として認められ、就農10年目に組合内でも市民権を得られるまでに至ったと伊藤さん。
●生乳出荷で生活を
「私はサーフィンが得意ではないので波にうまく乗れない」――そう自己評価をする伊藤さん。それは時代のトレンドに左右されて波に飲まれることを避けることを意味します。伊藤さんは、波乱のスタートを切ったときから、「あくまでも生乳出荷の乳代で生活すること。副産物(個体販売)の収益をあてにしない経営をする」をポリシーとしてきました。「それが自分にできる一番の方法」と、就農以来いかにバランス良く喰わせ、個体乳量を上げるかを心情としてきたそう。
●ほしい品質のもの=適正価格
デイリーパラダイスは全量購入飼料の経営。飼料価格が高騰・高止まりするなかでダメージはいかほどだったのか。伊藤さんは「2年前の決算、都府県の酪農の9割が赤字と言われたその時期でも、うちは黒字だった」と教えてくれました。「当時は子牛の価格が高かったため、周囲からは『個体販売にも取り組みなよ』と言われたが、『生乳一本でいく』という信念は変わらなかった」と言います。その後、子牛の価格は下落。「やはり波乗りは苦手なようだ」とはにかみます。
「粗飼料は自分がほしい品質のものを入手する。それが世間では高いと評価されても、自分にとっては適正価格であり、高いと思ったことはない」と飼料へのこだわりを話します。ただ、粗飼料も農産物ゆえ、品質は一定ではありません。在庫のなかから硬さや成分をブレンドして、給与する際になるべく一定の品質になるように、とくにルーメンの通過速度を安定させるよう調整していると伊藤さん。粗飼料を質メイン、価格は次点とすることで高乳量をキープし、売り上げをキープ、「生乳で生活する」の循環を守っています。
●高繁殖が積極的淘汰と牛群レベルアップに
高く安定した収益性を支えてきたのは、根底に繁殖に力を注いできたことがあります。行動管理センサーの導入や、10年前からは獣医師が毎日往診してくれるようになったことで、繁殖がうまく回らない牛の摘発と処置が迅速に行なえるようになったため繁殖成績は高位安定。分娩間隔が短縮されることによる個体乳量の増は、出荷乳量の増に直結します。
全頭にホルスタインを授精し、後継牛をしっかりと確保することで積極的な更新も可能になりました。ちなみに更新率は35から36%と比較的高いのは、この積極的更新を反映した結果です。
●税理士とはわかりやすい共通スコアで
牧場を運営するうえでパートナーの一人となるのは税理士。経営数値に明るく、経営の方向性を一緒に確認する大切な存在だと伊藤さん。その税理士と農場の現状を把握するために、伊藤さんと税理士が注目したのは、「1日の出荷乳量」と「1頭当たりの年間乳量」だと教えてくれました。農家にとっても税理士にとっても最もわかりやすいのがこの二つだと言います。そして「生産乳量と出荷乳量を把握すること」も加えます。出荷乳量が、すなわち売り上げにつながり、生産乳量が今後の行動を考える基礎となると教えてくれました。
就農以来変わらないポリシーと、逆境下でスタートしたデイリーパラダイスは、今も堅実に成長しています。
※詳しくは『Dairy Japan』2024年9月号で
PROFILE/ 筆者プロフィール

前田朋宏Tomohiro Maeda
Dairy Japan編集部・都内在住。
取材ではいつも「へぇ!」と驚かされることばかり。
業界に入って二十数年。普遍的技術、最新の技術、知恵と工夫、さまざまな側面があるから酪農は楽しい!