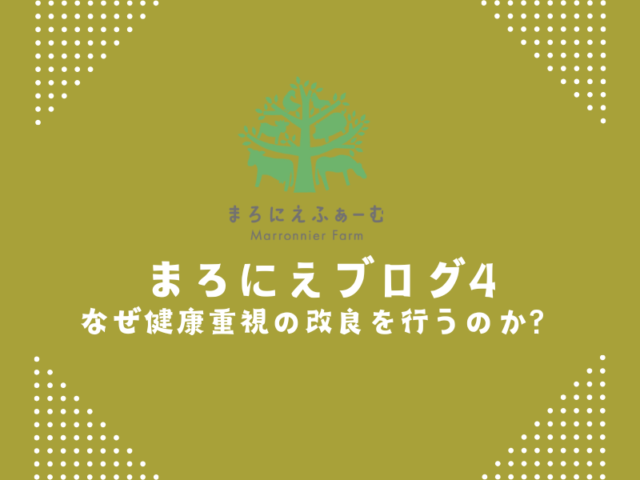こんにちは。北海道標茶町で、土壌改良資材の販売はじめ、酪農家さんのサポート業務をしています「soil」の今村太一です。このブログでは、私達が普段向き合っている「草・土・菌」を中心に、酪農場がより豊かになるような情報を共有させていただきます。
厳しい情勢で何ができるか?
まずは、大前提としてのお話をさせてください。酪農の経営は、正直なところ停滞……いや、衰退していると言っても、あながち間違いではないと思います。酪農家戸数、牛の頭数はともに、年々減ってきています。
技術の進歩があっても、それによって得られる利益には限りがあり、成長率は横ばい。ある意味で「頭打ち」状態です。そこに加えて、物価の高騰や燃料費の上昇が経営を圧迫していて、「このままでは厳しい」と感じている方も多いのではないでしょうか?
本当に良い土とは?
私はかつて、飼料会社に10年以上勤めてきました。その中で、「化学肥料をどれだけ入れているか(充足率)」と「畑の更新」が、良い草を育てるために必要な良い土の条件だと、ずっと信じて疑いませんでした。
でも、土壌菌を育てる父の影響から“土の中の世界”を学んでいくと、自分の中の常識がひっくり返るような衝撃を受けることになりました。
化学肥料と畑の更新は、酪農家さんにとって、「草の収量の最大化」が目的になりがちです。でも、それが「経営の最大化」につながっているかというと……実は、そうとも限りません。
安定して同じような収量が出ていても、毎年のように起きる自然災害や病気の被害。さらに、SDGsやパリ協定といった環境対策の流れ、飼料や肥料の原材料が枯渇してきていること、工場のトラブルや戦争の影響……。数え始めたらキリがないほど、価格が高騰する要因はあちこちにあります。外部環境に頼る状況では、経営が苦しくなるのも当然だと思います。
今までの常識から脱して考えてみる
そこで私は「変化」としてのご提案をしたいのです。今までにはなかった「アンチテーゼ」つまり、真逆の視点を取り入れることが必要じゃないか、と。
いつの時代も、生き残るのは「強いもの」ではなく、「変化に対応できるもの」だと言われます。あえて“足す”のではなく、“引く”ことで経営を安定させる道もあるのではないでしょうか。
その答えの一つが、「良い土をつくること」だと私は思っています。
良い土をつくることで、柔らかくて、糖度の高い草が育ちます。
ホルスタインのエサのうち、約半分が牧草なので、吸収されやすくて、糖分の高い牧草がどれだけ価値があるか……酪農家の皆さんなら、誰よりもよくご存知のはずです。
では、「良い土」と聞いて、どんな土を思い浮かべますか?
土の反対は「砂」ですよね。砂の上で植物は上手く育ちません。
つまり、土というのは生き物が住んでいる場所。そして、その生き物達が暮らしやすい環境を整えることこそが、私達ができることではないかと思うのです。
私が信じていた「化学肥料」と「畑の更新」は、土の中の生き物達にとって、メリットにならないと、今では強く思います。
糞尿も処理ではなく活用に
「処理が大変だ」と言われる堆肥やスラリー、そしてバイオガスの消化液。
これらの特性をよく理解して上手に使うことで、処理ではなく「利用」することができ、ミミズや土壌菌をしっかり土の中に定着させることができます。
もちろん、完全な有機だけを目指すということではありません。化学肥料に頼りきるのでもなく、有機一辺倒に振りきるのでもない。まずは、今ある牧場の現状に合わせて、循環型の考え方と現代技術を組み合わせた「ハイブリッドな農業」を目指すこと。
それが、これからの酪農経営の一つの活路になると、私は信じています。
次回は、化学と有機、それぞれのメリットとデメリットについて、具体的に見ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
この記事が面白かったらシェアしてください!
↓ ↓ ↓
PROFILE/ 筆者プロフィール
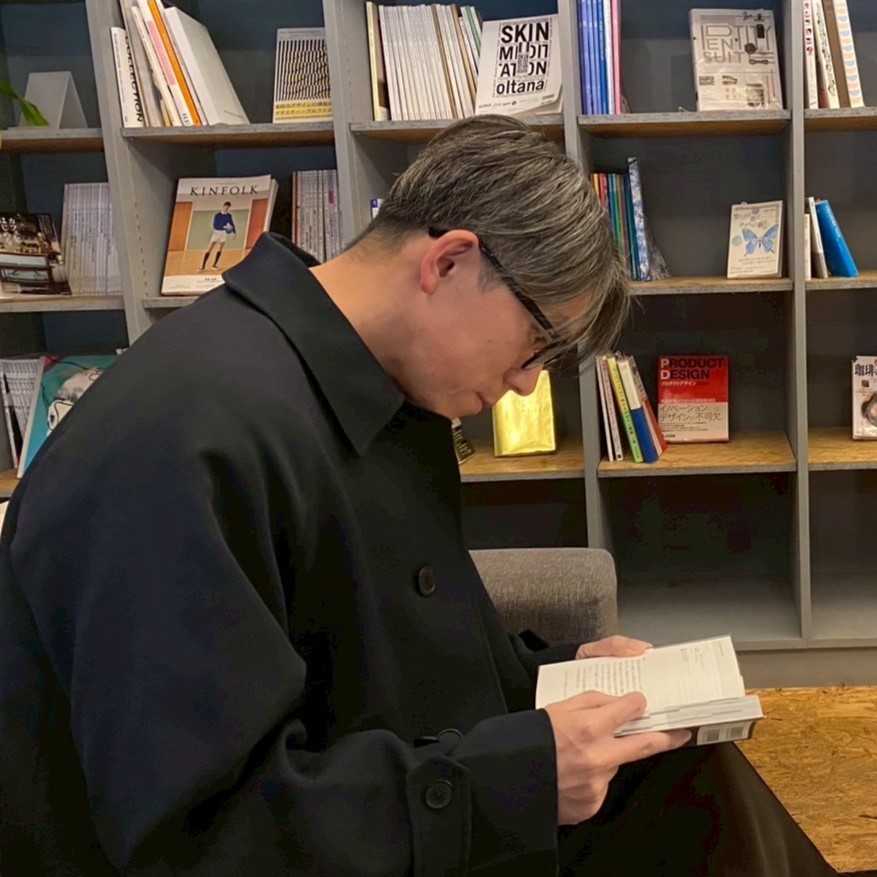
今村 太一Imamura Taichi
標茶町を拠点に、土壌改良資材の販売や周辺酪農家さんのサポートをする「soil」の代表。飼料会社に13年勤めた後、ドライフラワーやマツエク、ネイルのお店を経営。弟と一緒にsoilを立ち上げ、今は土や牛、人とのつながりを大事にしながら活動中。
経営やコーチング、微生物の話が好きです。「目の前の人に丁寧に」が大切にしている想いです。