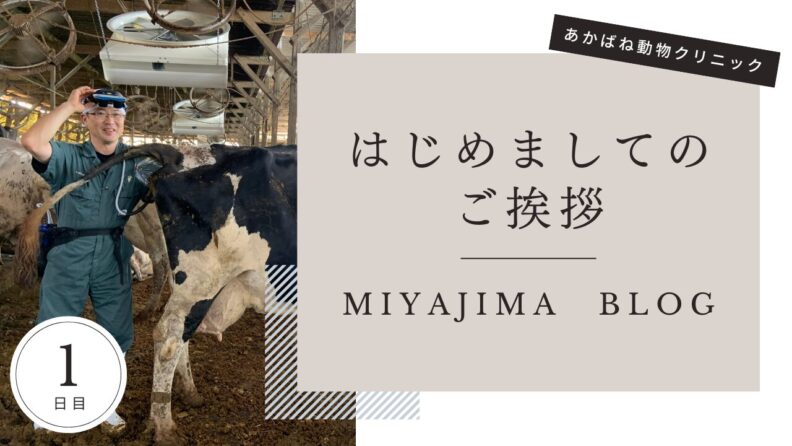前回は、哺育・育成期の管理の考え方について、私が実践している方法をご紹介しました。そして、「やはり子牛を生む前の管理が大事」というところに落ち着きました。
今回から、母牛管理や精液選定について、私が実践していることをご紹介します。
後継牛の選び方?
まずは、出生前の管理が重要です。なかでも、母牛選定や精液選定が最初の課題になると思います。
うちでは後継牛の母牛選定は、まずは未経産牛が基本になります。未経産に性選別精液を使用して、後継牛の改良速度を速めることを狙っての選択になります。
就農1年目は全頭から後継牛を取っていましたが、2年目からは乳検の改良情報を見ながら、基本は経産牛から後継牛を産ませずに、未経産牛からのみ後継牛を確保していました。
近年はゲノム検査を開始したので、ゲノムの数値を参考に判断します。良い初妊牛は、分娩してから初産牛として搾乳から授精を迎えるまでの期間に、生産性を考慮してから判断できるようになりました。ゲノムの数値が良く、分娩後の産乳成績が良い牛には性選別精液を使用して後継牛を確保しています。
使用する精液は、当初は信頼度が高い国内種雄牛の精液を使用していましたが、近年はゲノムでハッキリ数値がわかるので、より良い数値を求めて海外のヤングサイアを使用しています。
考え方を変更した
私は当初、客観的な改良情報のデータ数値よりも、実際の牛を観察して管理したうえでの主観的な判断をしていて、改良情報の数値はそこまで重要視していませんでした。
しかし近年ゲノム検査を開始したことで、数値の重要性を認識して考えを一新しました。実際に数値がわかった状態で数値を意識して牛達を観察しながら仕事をすると、明らかに能力に差があることが確認できました。それきっかけとなり、今では数値は重要だと考えるようになりました。
うちの牛群は現在、5産以上の産次を重ねた牛達と、改良されてきた高ゲノムの初産の牛達が混在状況です。就農して数年はゲノム検査をしていませんでしたが、後代検定の精液を利用していたことで、毎年数頭は検査されていました。そして現在ゲノム検査を開始した段階で、その数値を比較することができました。産次を重ねた牛達と、現在の初産牛や未経産だと、ゲノムの総合指数で2倍近く違う牛達が存在しています。
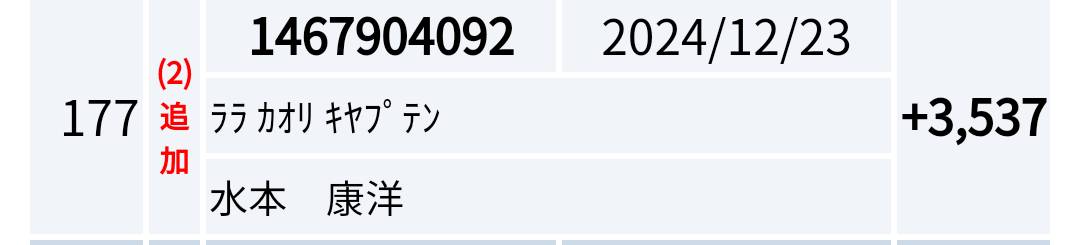
数値を意識した改良することの重要性がハッキリと理解できました。搾乳時の乳量、乳成分の違いはハッキリ数字でわかります。

子牛こそ改良の重要性がある
しかし、私個人的には、子牛のほうがより改良の重要性を感じています。分娩時の強さや哺乳・育成時の管理のしやすさなどは、ゲノム検査による精液の進化に伴い年々進化が進んでいると思います。
なので、より良い牛群を構成するうえでは、母牛選定、精液選定が最初の課題になると思います。
そして、選定して授精し、受胎した「胎子」の数値の最大値を出すためには、分娩前の管理がより重要になると考えています。
次回は、分娩前管理について私の取り組みをご紹介します!