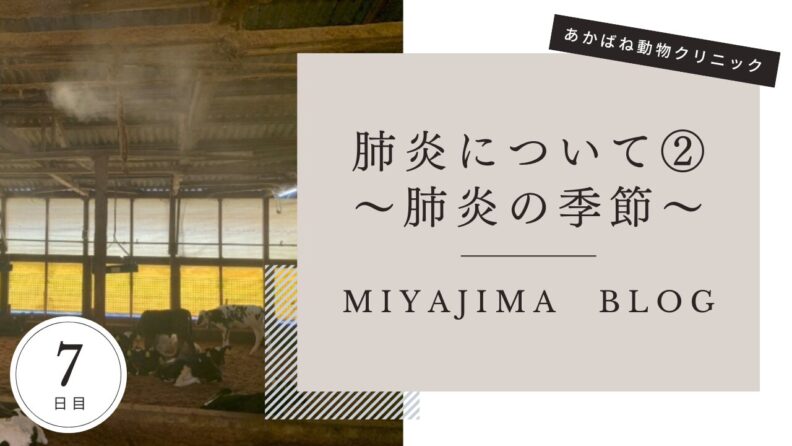先月、北海道内で酪農を営んでいる卒業生と久しぶりに話しをする機会がありました。一人は実家の後継者、もう一人は酪農家に嫁いだばかりで可愛い赤ちゃんも連れてきてくれました。四方山話に花が咲いた頃、牛舎の新築やリフォームの話になりました。
牛舎更新時期が来るも……
二人とも、古い牛舎で営農しているということで、既存牛舎に何らかの手を加えなければいけない時期にきているとのことでした。新築するのか、リフォームするのか、敷地や資金が絡み難しい問題です。
私は友人、知人のおかげで道内や内地の酪農場を視察する機会をいただいています。訪問先は民間の酪農家から、学校や試験場といった公的機関まで多岐にわたります。古くてもシステムとして見事な牛舎から、新しく新築した牛舎であっても欠点が山積みの牛舎まで、それこそピンからキリまで存在します。
古くて欠点がある牛舎はこれからどのように改良していけば良いかという、悩みもありますが、前向きに捉えるとワクワクする気持ちになれます。
一方、新しいのに欠点が目立つ牛舎、とくにそれが基礎や構造物といった根幹部分に見られる牛舎では、正直なところ今後数十年それと付き合っていかねばならず、気持ちが暗くなります。

酪農学園大学の農場では、マットとパーティションを交換しました。
いずれにしても慎重に
私の師匠達は、口々に言います。牛舎を建てる前に、プロに相談して、何度も検討会を開き、あらゆる角度からシミュレーションしなければいけないと。それだけやっても、欠点が皆無の牛舎はできないとも言います。
このことはほぼ間違いがないようで、補助金などの事業申請が迫っていて、深く検討する間もなく設計した牛舎では欠点が目立つような気がします。酪農場をシステムとして捉えずに、単体の牛舎として設計した場合にも、動線や拡張性といった部分で課題が目立つケースが多くなるように感じます。
そんなこんなを二人の若い酪農人と、時が経つのも忘れて話し込んでしまいました。彼らの酪農場がどのように変化していくのか、これからが楽しみです。
最後に私ごとになりますが、報告をさせてください。
4月から、私は酪農大から日本大学生物資源科学部に転職いたします。所属が変わり、住まいも北海道から神奈川に転居となりますが、引き続きルミノロジーから酪農生産システムに関してつれづれに語っていこうと思っています(編集部にクビにならなければですが、笑)。酪農大時代は生産者、師匠の方々、学生、大学農場技師をはじめとする関係者の皆さまに育ててもらい、今の私があります。これからは関東の人間になりますが、道産子の誇りを忘れずに、酪農産業に貢献していくつもりです。今後ともよろしくお願いいたします!
この記事が面白かったらシェアしてください!
↓ ↓ ↓
PROFILE/ 筆者プロフィール

泉 賢一Kenichi Izumi
1971年、札幌市のラーメン屋に産まれる。1浪の末、北大に入学。畜産学科で草から畜産物を生産する反芻動物のロマンに魅了される。修士修了後、十勝の酪農家で1年間実習し、酪農学園大学附属農場助手として採用される。ルミノロジー研究室の指導教員として学生教育と研究に取り組むかたわらで、酪農大牛群の栄養管理に携わる。2025年4月、27年間努めた酪農大を退職し、日本大学生物資源科学部に転職する。現在はアグリサイエンス学科畜産学研究室の教授。専門はルーメンを健康にする飼養管理。最近ハマっていることは料理と美しい弁当を作ること。