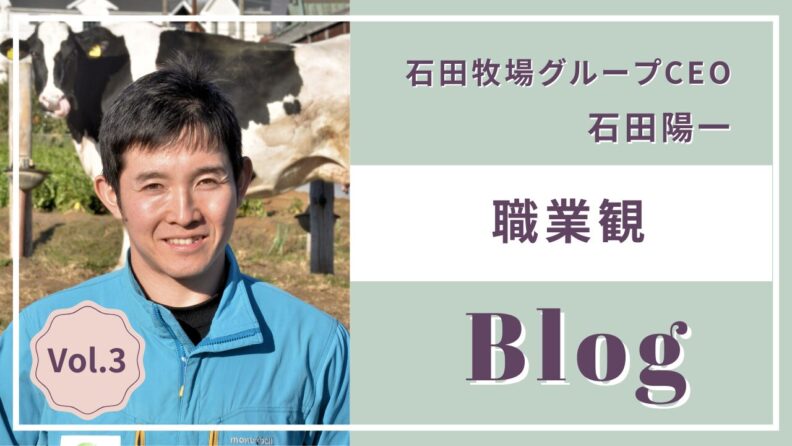『Dairy Japan2024年12月号』では「自給飼料増産でコストダウン」を特集しました。そのなかから、兵庫県で耕畜連携に取り組み、地域貢献とコストダウンの双方に取り組む株式会社箸荷(はせがい)牧場の取り組みを紹介します。
営農組合と手を結ぶ
箸荷牧場が位置する兵庫県多可郡は県中央部に位置し、水田が多い地域。およそ3年前(取材当時)から、地域の営農組合などと協力して自給飼料の増産に取り組み始め、その面積を拡大させたといいます。
それに伴い、牧場外にフィードセンターを設け、自給飼料と発酵セミコンプリートなどを用いた給飼体系を作りました。デントコーンは搾乳牛のメニューに、イネWCSは乾乳牛のメニューにそれぞれ利用しています。
代表取締役の今中克憲さんは「主な目的は耕畜連携。地域への貢献のために自給飼料生産に取り組んでいる」とその理由を話します。自身が加入する箸荷営農組合のほか、近隣の営農組合に作付けと保全を依頼し、刈り取り・調製作業を自社で行なっています。

フィードセンター稼働により増頭を
デントコーンサイレージやイネWCSの保管、発酵セミコンプリートの調製・保管、TMR調製など飼料関係作業を効率的に行なえるよう建設したというフィードセンター。牛舎からは数分の距離で、調製したTMRを牧場にミキサーワゴンごと運んでいます。以前、牧場敷地内の一部にあった飼料保管庫と調製場は、フリーストール牛舎を延伸して増頭することに。
豆乳粕主体の発酵セミコンプリート
箸荷牧場で搾乳牛向けのメインとなる飼料は発酵セミコンプリート。豆乳粕にコーンなどを混ぜて発酵させるセミコンプリートで、食品製造副産物の有効活用にも一役買っています。発酵セミコンプリートを持つことで、日々の飼料調製を簡単にするだけでなく、年間を通じて安定した品質の基礎飼料を持つことができるほか、不測の事態に陥った際にも飼料給与を安定化できるメリットがあると言います。

積極的チャレンジで五つ星ホテルを
もともと開放型であったフリーストール牛舎は側面を覆い、大型の排気ファンとサイクロンファンによってハイブリッド換気牛舎にリニューアル。また細霧の導入によって夏場の牛舎環境の改善も果たしました。
「ライトコントロールが生産性を上げる」と聞けば搾乳牛舎をインダクションライトで長日管理に、その後は乾乳牛舎を遮光性の高いポリカボネートで覆い短日管理にリニューアルするなど、積極的に新しい技術を導入しています。
箸荷牧場のポリシーは「牛はお客様。そのお客様に最高のベッドとエサを提供するなど最高のおもてなしをする牛の五つ星ホテルを目指す」というもの。そのため、カウコンフォートの徹底に向けて日々アンテナを広げ、技術の向上に努めています。
PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa
DairyJapan編集部。
1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。
趣味はサッカー観戦。
取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。
皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。