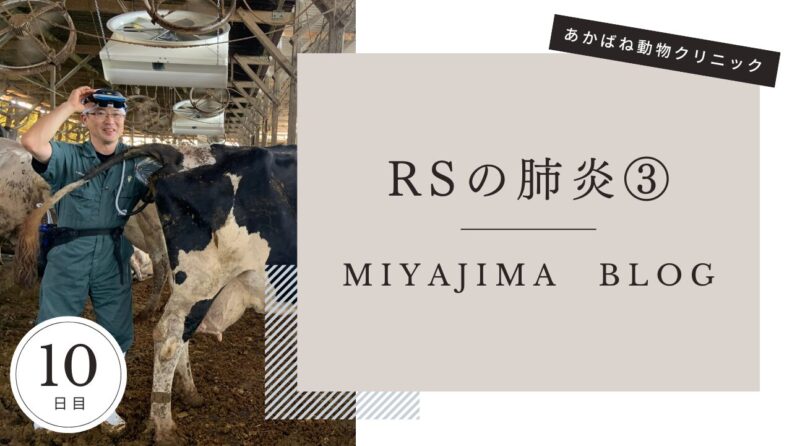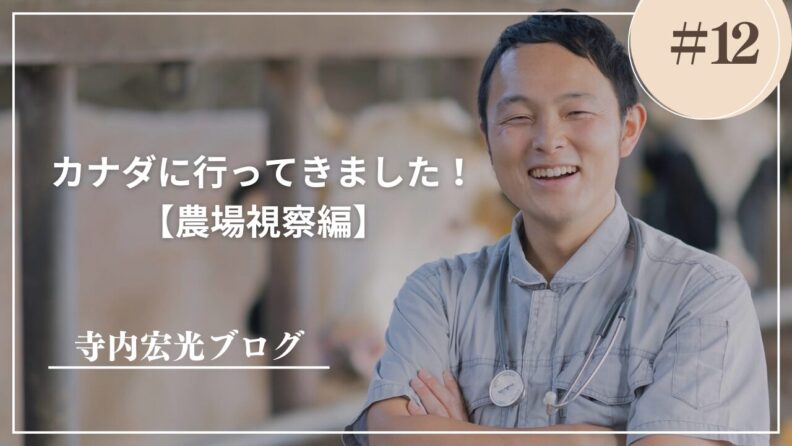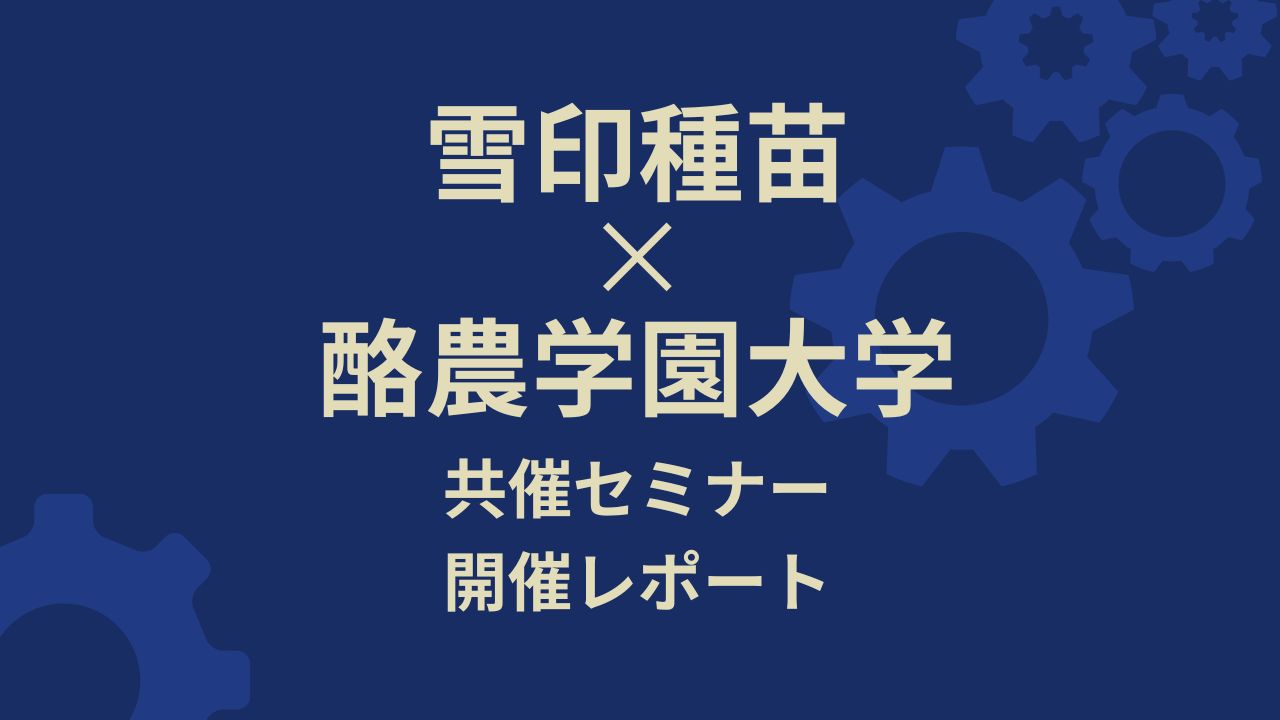
酪農学園大学・雪印種苗㈱共催 酪農セミナー開催
酪農学園大学と雪印種苗㈱は12月6日、「2024年度 酪農学園大学・雪印種苗株式会社共催 酪農セミナー」を開催しました。今回のテーマは「搾乳ロボット」で、以下の4つの講演が行われました。
1)搾乳ロボットの研究成果による酪農システムの進展(森田茂氏:酪農学園大学 循環農学類 家畜管理・行動学研究室・教授)
2)搾乳ロボットの経済性と欧州の搾乳ロボット事情の紹介(仙北谷康氏:帯広畜産大学 農業経済学分野・教授) 3)北米におけるロボット搾乳農場の計画時、設立時、運営時における鍵(高尾佳伸氏:ジンプロアニマルニュートリションジャパンインク テクニカル・セールスマネージャー)
4)搾乳ロボット牧場の現地事例(齊藤潔氏:釧路農業改良普及センター・所長)
搾乳ロボット導入は生産性向上が前提
講演2では、仙北谷氏が搾乳ロボット導入時の経済性について試算した結果を紹介しました。現在ミルキングパーラーで搾乳を行っている牧場がロボットを導入した場合の変化として、搾乳回数の増加による個体乳量の増加(約5%)、搾乳時間の削減による労働負担の軽減などが期待されると説明しました。
一方で、投資による一時的な所得減、減価償却費や修繕費の増加、乳量増加に伴う飼料費の増加など、ランニングコストの上昇が予測されるとも述べました。また、肉体的負担が軽減される一方で、余剰時間を牛群管理や経営改善に充てることが不可欠であり、「ただ導入すれば楽になる」という考えは誤りだと強調しました。
導入後の経営戦略として、少ない労働時間で高い所得を得ることを目的に、生乳の収益を現状から約20%増加させることが求められます。そのためには、綿密な栄養管理や牛群管理が重要となります。さらに、初期10年の元金据え置き期間中に貯蓄を進め、後半に備えるキャッシュフロー計画を策定することが成功の鍵です。

牛の行動最適化が鍵
講演3では、高尾氏が北米の事例を基に、搾乳ロボット導入時のキーポイントについて解説しました。北米では2000頭以上の大規模農場でもロボット搾乳が導入されており、その際の課題として、ロボットへの移動をスムーズにすることが重要であると指摘しました。
牛舎のレイアウトが悪かったり、ベッドや通路の快適性が損なわれたりすると、通路の渋滞や蹄病が発生しやすくなり、生産乳量の低下や人による追い込み作業の増加につながります。
また、北米では「ロボット1台でどれだけの乳量を搾れるか」という考え方が経済性の指標とされ、牛の搾乳速度が重視される傾向があります。そのため、1日70kg生産する牛であっても、搾乳速度が遅い場合は淘汰対象となることもあると説明しました。
牛の健康維持には蹄病予防が重要であり、蹄浴槽の設置や、有機ミネラルを用いた栄養管理が求められます。搾乳ロボットは新規牛舎だけでなく、既存牛舎の改築時にも導入が増えており、その多様性が広がっています。そのため、導入にあたっては適切な施設設計や牛群管理の戦略がますます重要になると述べました。

PROFILE/ 筆者プロフィール

前田 真之介Shinnosuke Maeda
Dairy Japan編集部・北海道駐在。北海道内の魅力的な人・場所・牛・取り組みを求めて取材し、皆さんが前向きになれる情報共有をするべく活動しています。
取材の道中に美味しいアイスと絶景を探すのが好きです。
趣味はものづくりと外遊び。