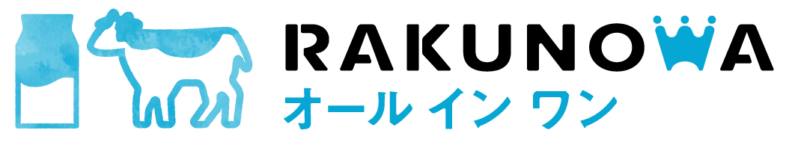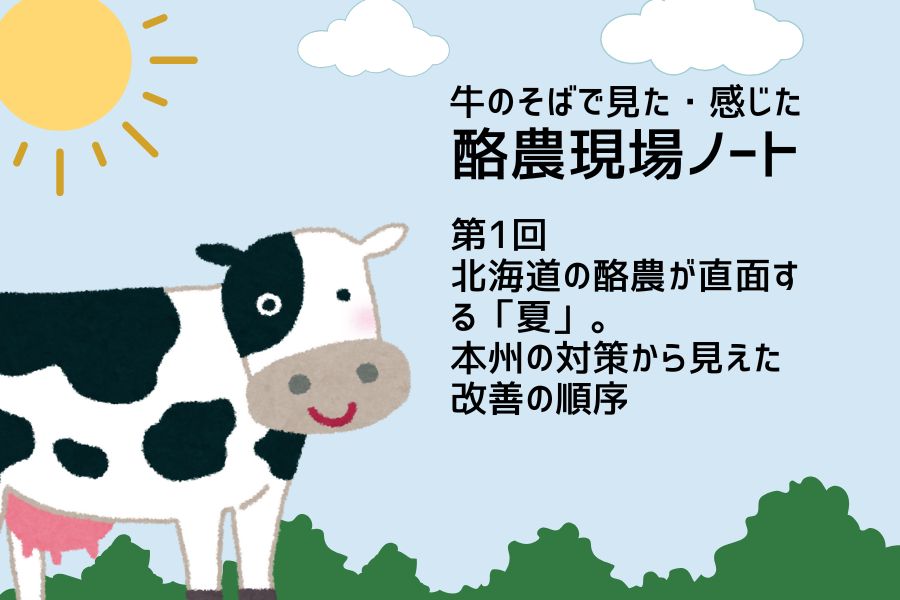
みなさん、はじめまして。十勝農業改良普及センターの住野と申します。北海道の普及センターに勤めて5年目の、酪農の世界にどっぷりはまった普及員です。
今回、普及員である私の視点から見た酪農現場について発信できる機会をいただきました。普及員の仕事についてはもちろん、現場で発見したものや農家さんとの話で学んだこと、セミナーで知ったことなどを普及員の視点も交えて発信したいと考えています。
仕事を始めて5年目。まだまだ修行中の身ですが、自分が酪農を学んでいくなかで感じた「面白い!」という気持ちを共有できれば嬉しいです。
今回は、この数年間、北海道ではおそらく最大のトピックスであろう暑熱について取り上げたいと思います。
令和5年、北海道でも連日30℃を超える猛暑の夏となりました。牛も人も疲れ果てた光景が記憶に新しいです。その暑さを受け、農場での暑熱対策が一気に加速しました。普及センターとしても暑熱対策について情報を発信すべく、令和6年に北関東(群馬県・埼玉県周辺)、令和7年に広島県と、北海道よりもはるかに暑い本州へ現地調査に向かいました。本州の暑熱対策を見た結果、①本州の桁違いな暑さ②とくに良いと感じた農場の様子③暑熱対策の順番について取り上げます。
本州の桁違いな暑さ
まず、本州と北海道の暑熱対策に対する認識の差を痛感しました。北関東の牧場で「とくに暑い2週間に分娩があると、必ずと言ってよいほど牛が死んでしまう」と聞いた時は衝撃でした。暑熱が「乳量」や「受胎しにくい」ではなく「牛の生死」に影響する本州は、暑熱対策に対しても本気度が高かったです。牛舎屋根の断熱材は当たり前で、送風・ミスト・ソーカー・クーラー、屋根散水からエサの添加剤とさまざまな工夫が施されていました。それぞれの牧場が牛の命を守るために考え抜かれた答えが、そこにありました。
とくに良いと感じた牧場
さまざまな対策を見るなかで、衝撃を受けた牧場がありました。その牧場では「牛が喰える環境を整えること」を重要視しており、とくに「換気・送風」に力を入れていました。トンネル換気を採用し、壁一面の排気ファンや牛に送風するためのファンがびっしり並んでいました。その結果、牧場の入り口に立つと、帽子を押さえないといけないほどの風が流れ、牛の様子を見ると、38℃の外気温を感じさせない腹の張り、横臥率、反芻、毛艶の良さでした。エサにも何か秘密があるのかと訊ねると、「添加剤は重曹くらいかな」とのこと。牛が喰える環境を整えると、エサもシンプルにできる可能性と、その環境作りには換気と送風が非常に重要であることを実感しました。
暑熱対策の順番
本州を見て感じたもう一つのことは、「暑熱対策の最終形」であることです。夏=牛の生死が分かれる季節である本州と比較すると、北海道はまだそこまでの気温ではないですし、冬の対策も考えなければなりません。これは、本州から学んだことを分析し、順序立てて取り入れていく時間的猶予が残っていることだと思います。
その中で、換気と送風の重要性は確かです。換気が整うだけで、ミストの利用効率もぐんと上がります。暑さが過ぎ、夏場の記憶が薄れていく今ですが、今年の夏を振り返り、来年の暑熱対策を再考する方は多いと思います。そんな今、換気と送風の重要性について(十分実感されている方も多いと思いますが)感じていただければ嬉しいです。
今回取り上げた本州の対策も含めた暑熱対策のガイドブックを普及センターで作成しました。十勝農業改良普及センターのHPで見ることができますので、ぜひご覧ください。(十勝農業改良普及センターHP:https://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/siryou_R6_shonetsutaisaku.html)
このような形で、細々と書いていけたらと思っています。なんだか面白いことをやっている普及員もいるのだと思っていただけるよう精進します。これからどうぞよろしくお願いいたします!
PROFILE/ 筆者プロフィール

住野 麻子Sumino Asako
十勝農業改良普及センター十勝南部支所で農業改良普及員として活躍中。
兵庫県神戸市生まれ。酪農に興味を持ち、大学進学を機に北海道へ。大学卒業後、十勝農業改良普及センターに就職。現在は酪農の面白さにはまり、牛漬けの日々を送っている。現場をより良くできる普及員となれるよう奮闘中。