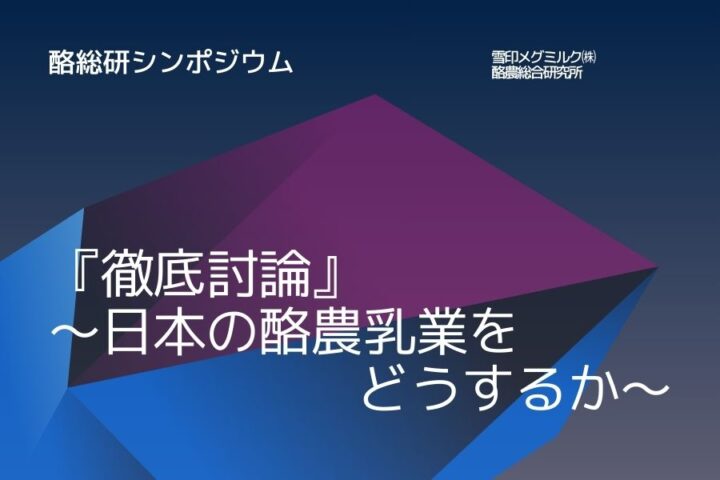こんにちは! FarmEnJineラジオの第5回目のご案内です!
牧場をうまく回すには、まず「牛が気持ちよく過ごせること(カウコンフォート)」と「栄養設計」がセットで考えられていること。
今回のFarmEnJineラジオでは、小林悟さんが米国視察で見てきた内容のフィードバックを中心にお話ししました。
「消化率60%超のグラスサイレージ」「粗飼料比率50%〜」「TMRを安定させるための現場ルール」など、
すぐ現場に応用できるヒントを会話形式で深掘りしています。
28〜35日サイクルで4〜5回刈る。北海道でも再現できるグラス設計
見に行った牧場では、アルファルファ・クローバー・オーチャード・イタリアンをミックスし、
28〜35日おきに4〜5回刈りを実践。
30時間消化率で60%を超えるグラスサイレージを確保し、粗飼料比率50〜60%を維持していました。
ポイントは、「質の高い草を回数で積み上げる」こと。
日本でも、ロールサイレージを使うなどコストを抑えた代替策で十分再現可能とのことです。
TMRの鍵は“時間”じゃない、“安定”だ。ミキシングの「正解」は牧場ごとに違う
TMR(混合飼料)は、混ぜる時間の長さではなく毎日同じ水準を保つことが最重要。
「10分の日もあれば40分の日もある」――これが一番危ない。
ミキサーの種類(リール型・縦型・横型)に合わせ、パーティクルセパレーターで粒度を確認し、
最初と最後のサンプルを比べて偏りを見れば、牛が強い弱いで“おいしい部分を奪い合う”ことも防げます。
乾草は「おいしさ×長さ」で扱いを変える
粗飼料は美味しくない草ほど、短く切るのが鉄則。
オーツヘイのように嗜好性が高い草は、多少長くても食べます。一方で、ウィートストローのような味の薄い草は長いと残ります。だからこそ、「短く切る」「短い製品を買う」。
TMRに混ぜた時に“鼻で寄せられない”長さを重視します。
みなさんからたくさんの質問をいただきありがとうございます。質問に対する回答も、ラジオの中でしていきますので、ぜひチェックをお願いいたします!
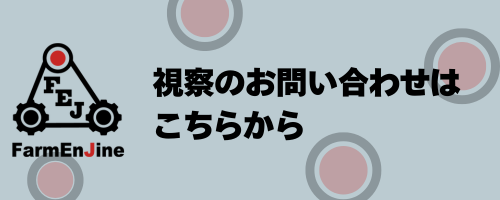
PROFILE/ 筆者プロフィール

大塚 優磨Otsuka Yuma
株式会社FarmEnJine代表。
「酪農業界にエンジンをかける」をモットーに、栄養・繁殖それぞれの専門的視点での酪農経営の課題の洗い出しや、酪農経営のゴール設定、など、「本当に酪農家を豊かにする」ためのサポートを行なう。
スタートアップの企業につき、Youtubeで酪農に役立つ情報を公開中