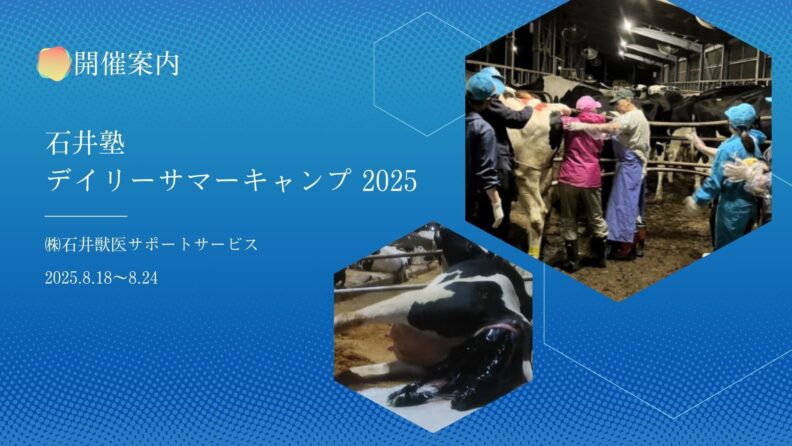神奈川県に移住して楽しみにしていたことの一つがスポーツ観戦です。プロ野球やJリーグを中心に、ハマスタ(横浜スタジアム)や神宮球場へ足を運んだり、サッカーやラグビーの試合も楽しんダリと、こちらでの生活を満喫しています。とはいえ、やっぱり気になるのはファイターズとコンサドーレ。やはり急に地元チームへ愛着を持つのは難しいようです。そこで、地域に早く溶け込もうと、夜な夜な盛り場に出て地元の常連さんたちと交流しています。
健康診断と“見えないサイン”
さて、私は年1回の健康診断受診が義務づけられており、そこで何らかの異変が見つかると、精密検査や治療へと進んでいきます。
なかには「俺はここ十年以上、医者にかかったことないわ」と“豪語”なさる方もいらっしゃいますが、健康診断を受診していなければ、本当の健康体なのか、体調不良のサインを見落としているのかを判断することはできません。健康診断は病気のサインだけでなく、飲んだり食べたりといった栄養面の生活習慣も評価してくれます。栄養の摂りすぎで増える指標もあれば、栄養摂取不足(とくに蛋白質)も数値で示されます。
牛にとっての“健康診断”=牛群検定
それでは牛はどうでしょうか。人と同じように血液検査をすれば詳細は分かりますが、もっと簡単に健康や栄養状態を把握できるツールがあります。それが牛群検定です。
牛群検定では、毎日の乳から個体や群の栄養状態を評価できます。さらに過去から現在までの推移が示されるため、経営の方向性を考えるうえでも大きな手がかりとなります。
私もかつて、検定未加入の牧場から飼養管理の助言を求められたことがあります。その際は個体データがなく、バルク乳の情報のみでコメントしましたが、的確だったかは分かりませんでした。やはり詳細なデータがあるかどうかは大きな違いです。

進化する検定と改善スピード
最近の検定では栄養評価の指標が充実してきています。ルーメン発酵の適正を示すデノボ脂肪酸、エネルギーバランスを評価するBHB(ベータヒドロキシ酪酸)、プレフォーム脂肪酸などの項目がアウトプットされます。従来の乳質や繁殖成績とあわせて観察すれば、牧場現場で注目すべきポイントが見えてきます。
牛群検定のデータと現場の観察結果を組み合わせることで、より的を絞った対策が可能になります。
投資としての価値
昨今、ゲノム情報を使うことで牛群の改良スピードが爆上がりしていることは周知のとおりですが、それは「数値化できなかった情報を育種改良に加えた」結果です。同じように、検定非加入の農場が検定成績を導入すれば、飼養管理の改善スピードを格段に高められるはずです。
コスト面での負担を考えても、投資としては決して悪くないと私は考えています。
牛群検定は「牧場の健康診断」。そのデータが、未来の生産と経営を支える大きなヒントになるのではないでしょうか。
PROFILE/ 筆者プロフィール

泉 賢一Kenichi Izumi
1971年、札幌市のラーメン屋に産まれる。1浪の末、北大に入学。畜産学科で草から畜産物を生産する反芻動物のロマンに魅了される。修士修了後、十勝の酪農家で1年間実習し、酪農学園大学附属農場助手として採用される。ルミノロジー研究室の指導教員として学生教育と研究に取り組むかたわらで、酪農大牛群の栄養管理に携わる。2025年4月、27年間努めた酪農大を退職し、日本大学生物資源科学部に転職する。現在はアグリサイエンス学科畜産学研究室の教授。専門はルーメンを健康にする飼養管理。最近ハマっていることは料理と美しい弁当を作ること。