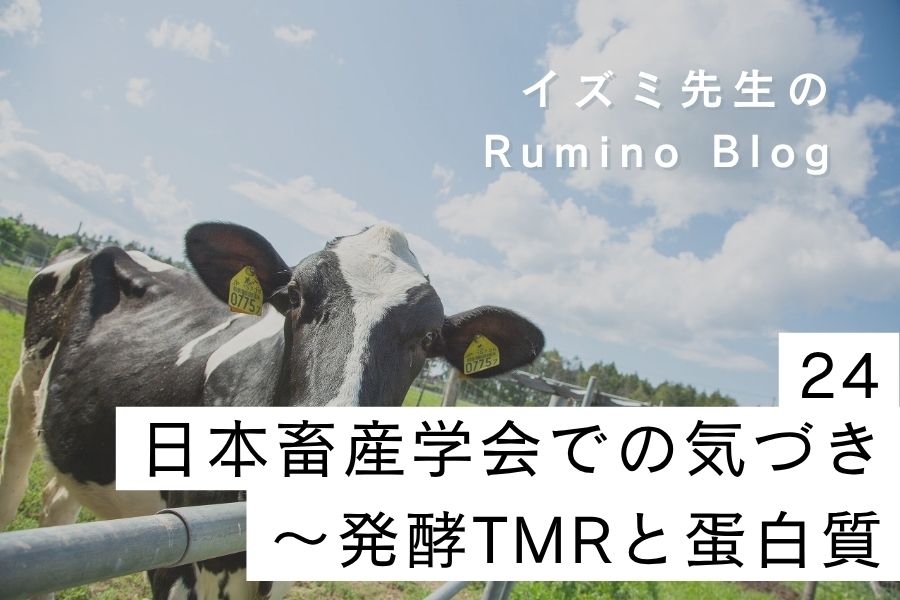
こんにちは、日大の泉です。
日本畜産学会の大会は毎年9月に開催されますが、今年の当番大学は岐阜大学でした。私も参加し、昨年の研究成果を発表してきました。内容は「早刈り牧草サイレージを多給することで飼料コストが下がり、IOFC(乳代から飼料費を差し引いた粗利益)が増える」というものです。こちらの詳細はまたの機会に譲り、今回は聴講したなかで興味深かった発表をご紹介します。
発酵TMRと蛋白質分解の問題
特に印象に残ったのは、広島県の畜産技術センター・広島県酪・全酪連の共同研究です。テーマは「発酵TMR中の蛋白質の分解程度と保存期間中の気温」。
試験結果によると、発酵TMRを高温条件下で長期間保管するとタンパク質が過度に分解され、溶解性タンパク質(SIP)が急増するとのことでした。実際に夏場、発酵TMRを給与する酪農家から「乳中尿素態窒素(MUN)が異常に高い」という相談があり、牛群でMUNが20mg/dlほどまで上昇した事例が報告されていました(通常は10〜15くらい)。

ルーメン内で何が起きているのか
溶解性蛋白質はルーメン内で急速に発酵し、大量のアンモニアを生み出します。アンモニアは微生物の栄養源として不可欠ですが、過剰に発生すると使い切れず、ルーメン壁から吸収されてしまいます。
吸収されたアンモニアは肝臓で尿素に変換され乳中に現れます。これがMUNです。この変換過程ではエネルギーが消費されるため、乳量減や牛体の削痩につながりかねません。さらにアンモニアは毒性を持つため、肝臓への負担も無視できません。
要するに、溶解性蛋白質が多くMUNが高い状況は、牛にも乳生産にも好ましくないのです。
試験結果と対策の方向性
研究チームは原因と対策を探りました。気温30℃の条件下で28日、56日と発酵期間が延びるほど、フレッシュTMR(0日)と比べてSIPが上昇することを確認。また、高温でとくに分解が速い原料の特定も進めていました。
現場からの疑問に研究で応答するアプローチが印象的で、私自身も共感するところが多かったです。
余談ですが、岐阜は酒もうまく、鮎やジビエも堪能でき、学会前後大変充実したものになりました。
研究現場と生産現場をつなぐ、こうした試験報告は今後ますます重要になりそうです。
PROFILE/ 筆者プロフィール

泉 賢一Kenichi Izumi
1971年、札幌市のラーメン屋に産まれる。1浪の末、北大に入学。畜産学科で草から畜産物を生産する反芻動物のロマンに魅了される。修士修了後、十勝の酪農家で1年間実習し、酪農学園大学附属農場助手として採用される。ルミノロジー研究室の指導教員として学生教育と研究に取り組むかたわらで、酪農大牛群の栄養管理に携わる。2025年4月、27年間努めた酪農大を退職し、日本大学生物資源科学部に転職する。現在はアグリサイエンス学科畜産学研究室の教授。専門はルーメンを健康にする飼養管理。最近ハマっていることは料理と美しい弁当を作ること。





