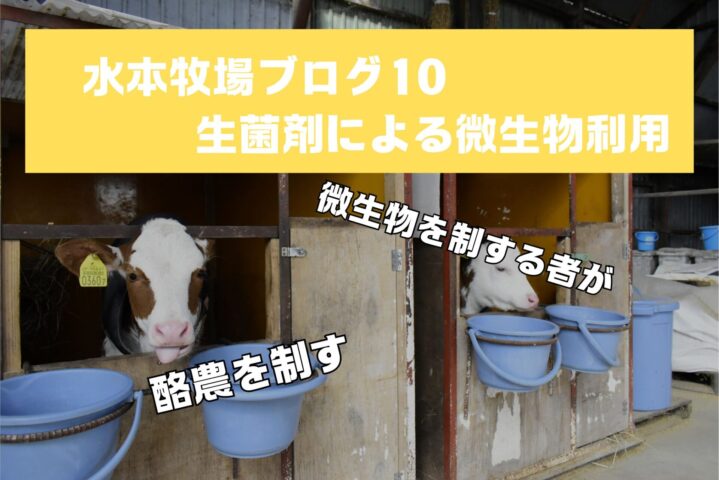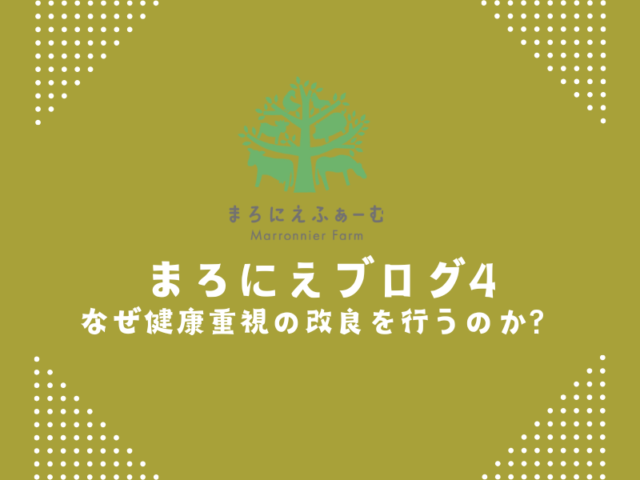3種の自給飼料で牛に無理なく乳量アップ ― 村﨑牧場の挑戦 ―

購入飼料価格が高止まりする今、飼料の自給率をどう高めるかは多くの酪農家にとっての課題です。「草で乳を搾る」ことを目指し、十数年にわたって粗飼料体系を見直してきたのが、北海道広尾郡大樹町にある村﨑牧場。チモシー・オーチャードグラス・デントコーンをバランス良く活用し、乳量と収益の両立を図る取り組みを取材しました。
粗飼料中心に切り替えたワケは?
村﨑隆一さんが粗飼料多給へ舵を切ったのは2013年。フリーストール導入で牛舎を拡張するなか、「個体乳量だけを追い続けると牛が持たない」と感じたことがきっかけでした。
当時はチモシーと露地デントコーンの組み合わせでしたが、収量・品質ともに課題が多く、タイミング良く雪印メグミルク(酪農総合研究所)とともに「オーチャードグラス主体の多草種混播」に挑戦を開始しました。

試行錯誤の末にたどり着いた理想形
取り組みは、オーチャードを少しずつ導入するところからスタート。播種や施肥、刈り取り時期などを酪総研と連携しながら見直し、現在は次の体系に落ち着きました。
- チモシー:2回刈り
- オーチャードグラス:3回刈り
- デントコーン:露地+マルチ栽培
収穫時期が分散されることで適期収穫がしやすくなり、収量も向上。栄養面でも、チモシーで繊維、オーチャードで蛋白、デントコーンでエネルギーを確保する理想的なバランスが整いました。
健康な牛群が利益を生む
この粗飼料中心の体系により、疾病が減少。獣医往診対応の時間が減り、そのぶん草地管理に注力できる好循環が生まれました。個体乳量は一時的に下がったものの、健康で長く働ける牛が増え、経営全体としては安定しています。
また、サイレージは草種ごとに別サイロで調製し、TMR成分が大きく変わらないよう工夫。ルーメン環境への負担も減らすことができています。

「基本に忠実」は、やっぱり強い
酪総研のサポートのもと、村﨑さんが10年以上取り組んできた草地改良。「正直、基本を守るのは面倒。でも、それが一番の近道だった」と振り返ります。
近年は再び個体乳量を上げる方針へ転換。デントコーンの給与量を増やしながらも、「無理をしすぎない」ことを大前提に、収支のバランスを見ながら理想の平均日乳量を35〜36kgと設定しています。

乳量の根本は「草」
村﨑牧場の取り組みは、「牛に無理をさせず、収益を伸ばす」経営のヒントが詰まっています。
重要なのは、外部の知見を取り入れながらも、自農場に合った形を根気よく作り上げていく姿勢。粗飼料の可能性を信じて丁寧に向き合うことで、購入飼料に頼りすぎない酪農が現実になりつつあります。
PROFILE/ 筆者プロフィール

前田 真之介Shinnosuke Maeda
Dairy Japan編集部・北海道駐在。北海道内の魅力的な人・場所・牛・取り組みを求めて取材し、皆さんが前向きになれる情報共有をするべく活動しています。
取材の道中に美味しいアイスと絶景を探すのが好きです。
趣味はものづくりと外遊び。