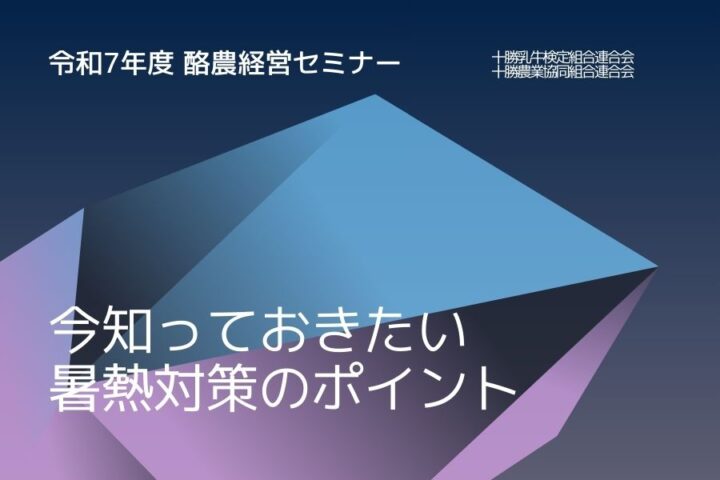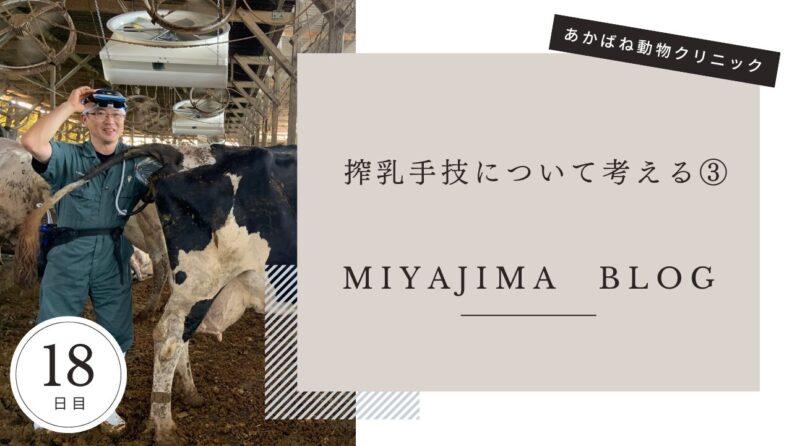『Dairy Japan』2025年1月号 p.50特集ルポ「2025年の営農計画」からルポ3「規模拡大は一段落 個体販売で収益増を」より香川県内で大規模経営を営む有限会社 赤松牧場。規模拡大に合わせるように、付帯する施設・設備を増強してきました。昨年新牛舎を稼働させたことで、新たな営農ビジョンを描き始めました。
きっかけは本牛舎建設から
赤松牧場は2017年に現在の本牛舎になるフリストール牛舎を稼働させ、規模拡大を図り始めました。130頭用フリーバーンから208頭用フリーストールへの移行に際して、赤松省一会長(当時社長)は、「全頭自家育成で増頭する」と決断。本牛舎建設の計画を立てた段階から精力的に性選別精液を使って後継牛を確保したとはいえ、満床に至るまでに約7年の歳月を費やしたといいます。
自家産後継牛にこだわったのは、「酪農の基本は乳牛であり、それを外部から調達することは本質から外れると考えた。子牛も初妊牛も相場に左右される。仮にそれで利益が出たとしても、酪農の利益ではなく、あくまでも預り金としてのもの。自家に合った乳牛を作り、管理することが酪農の基本的なスタンスだ」という理由からです。
そして本牛舎が稼働すれば、「以前の搾乳施設では効率的な搾乳が見込めない」と、翌2018年には新たなミルキングパーラーも稼働させました。
後継牛確保には育成牛舎が不可欠
性選別精液を利用しながら、以前をはるかに上回るペースで育成牛を管理するには、当然育成スペースが問題です。そこで赤松牧場では第2ステップとして育成牛舎の新築を果たしました。
育成牛舎が本格稼働すれば、初産牛も増え、搾乳頭数も育成頭数も増えます。次に課題となるのは糞尿処理だと判断し、堆肥舎も新たに作りました。
個体販売で収益増を
本牛舎とミルキングパーラー、そして育成舎と順調に施設を拡大してきた赤松牧場。さらに規模拡大を図るために、2023年5月には新たな牛舎を稼働させました。50ベッドのフリーストールにフリーバーンの乾乳エリアと哺育施設を備えた牛舎は、搾乳牛を増頭中。勲社長は「あと半年程度で搾乳牛は満床になる予定。それを見越して、現在は和牛受精卵移植やF1子牛の生産にも取り組み始めた。あくまでも自家産後継牛の確保が基本だが、今後は更新率を見ながら、F1や初妊牛の個体販売で収益を上げていきたい」とビジョンを話します。
これらの一連の増頭により、新牛舎がフルに稼働すれば、出荷乳量は現在の3000tから3500t程度に増える見込みです。
堆肥=宝の考え
赤松牧場は創業以来、堆肥は地力を強くする宝との考えで、近隣の耕種農家に有効活用してもらうように力を注いできました。現在は近隣の水稲農家でイネWCSを作付け・調製してもらい、耕畜連携を強固なものとしています。増頭に伴い糞尿の量が増える現在、「堆肥という宝が増えていく。この宝をもって近隣農家とさらに連携の和を広げ、自給飼料生産の拡大と県内農業への貢献をしていきたい」と勲社長はまとめます。
PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa
DairyJapan編集部。
1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。
趣味はサッカー観戦。
取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。
皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。