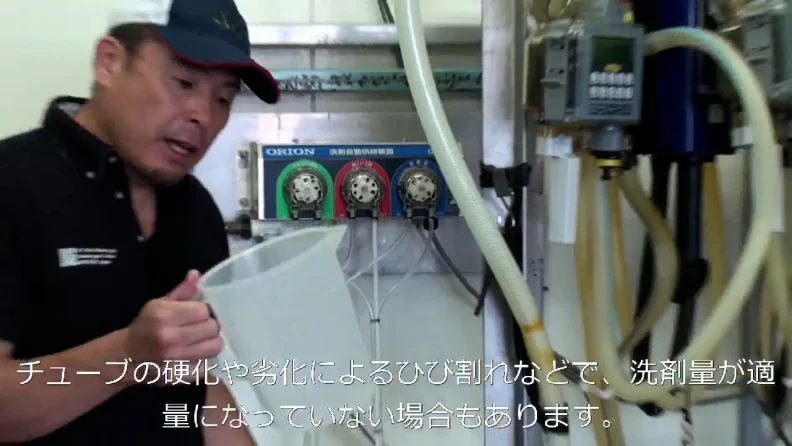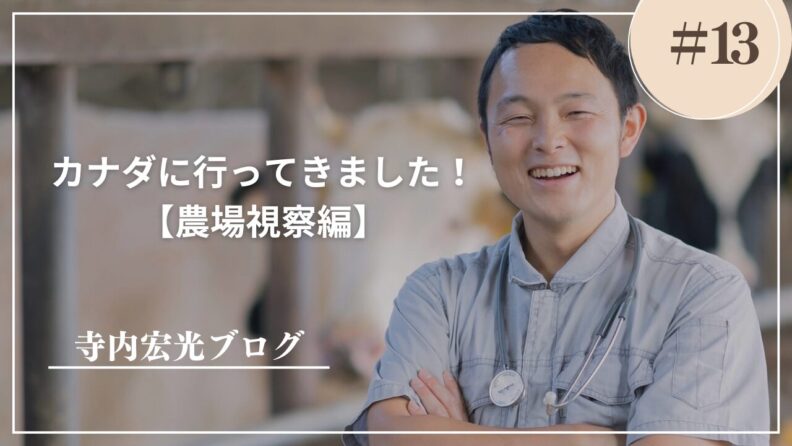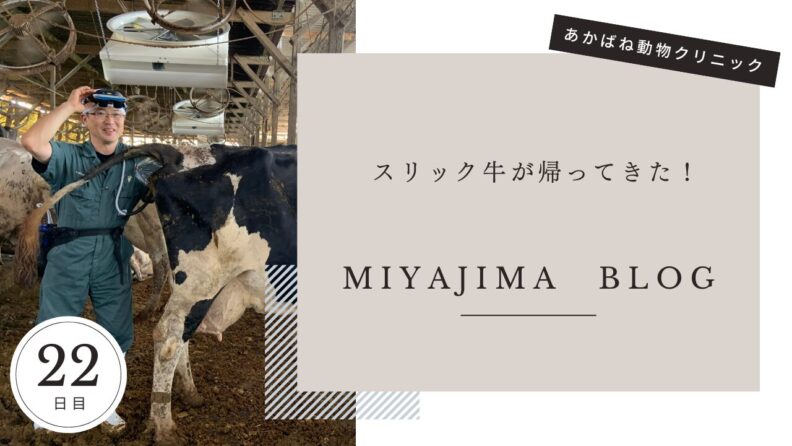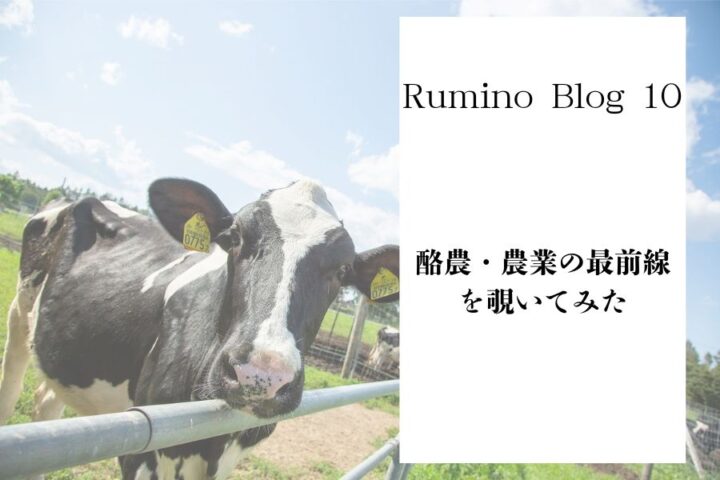十勝子牛研究会は2024年11月9日、帯広畜産大学で令和6年度の研修会を開催しました。同会は、子牛管理の技術向上を目的とし、十勝NOSAIの若手獣医師を中心に研究や学会発表の活発化を推進するために発足した団体です。子牛管理に関する幅広い情報を共有し、酪農業界のモチベーション向上に向けて活動しています。
今回の研修会では、同会の顧問である石井三都夫獣医師が、自身の著書『酪農家を楽にする 牛のためのお産BOOK』(デーリィ・ジャパン社)の内容を基に、分娩管理に関する講演を行いました。
分娩管理は経済性を大きく左右する
石井獣医師は、長年にわたり分娩に関する調査や研究を行ってきました。その経験をもとに、一つの酪農場における死産率が低下すると、農場の収入に大きな差が生まれることを解説しました。
十勝農協連との共同調査によると、死産率3%の牧場と8%の牧場では、空胎日数や個体販売額、生産乳量などの差により、年間約1,700万円の収益差が生じることがわかりました。死産率5%を超える牧場は、分娩管理に問題がある可能性が高いと指摘しています。
また、難産や死産が繁殖成績に与える影響についても説明しました。自然分娩や軽度な分娩介助を行った母牛の約半数は120日以内に妊娠するのに対し、重度な助産を受けた母牛は120日以内の妊娠が0頭、さらに死産を迎えた母牛は妊娠に至らなかったといいます。分娩の難易度が上がるにつれて繁殖成績が低下することが明らかになっています。
分娩の際に「軽度な介助」と「重度な助産」の違いを理解し、不要な助産を避け、本当に牽引が必要かどうかを慎重に見極めることが重要だと述べました。
きれいな牧場はうまくいく
分娩管理において、環境の清潔さは極めて重要な要素です。母牛が生活するエリアは、子牛にとっては“汚れた環境”となるため、生まれ落ちる場所の衛生管理が必須となります。これを満たすためには、清潔な分娩房の整備や、早めの母子分離が求められます。
新生子牛は必要な免疫を持ち合わせていません。免疫を吸収するためには腸に隙間があり、そこに免疫(初乳)を最初に届ける必要があります。しかし、分娩時の環境が悪いと、免疫より先に病原菌が侵入し、子牛が下痢や風邪などの健康トラブルを抱える原因となります。
理想的な分娩環境として、以下の条件を挙げました。
- クロースアップペンに隣接している
- 仲間が見える位置にある
- 単独で過ごせる空間がある
- 広く、壁がない
- 寝起きがしやすい
- 清潔である
- 水槽と飼槽が設置されている
- 監視カメラと吊り上げ設備が備わっている
また、できる限り素早い初乳給与と臍消毒が推奨されます。正常な分娩を迎え、不要な助産を避けるためには、分娩の徴候をよく観察し、じっくりと待つことが重要です。さらに、介助時に産道を傷つけないこと、子宮を汚さないことが、スムーズで良好な分娩につながるということでした。
今回の研修会を通じて、分娩管理の適切な手法が紹介され、参加者の意識向上につながる貴重な機会となりました。
PROFILE/ 筆者プロフィール

前田 真之介Shinnosuke Maeda
Dairy Japan編集部・北海道駐在。北海道内の魅力的な人・場所・牛・取り組みを求めて取材し、皆さんが前向きになれる情報共有をするべく活動しています。
取材の道中に美味しいアイスと絶景を探すのが好きです。
趣味はものづくりと外遊び。