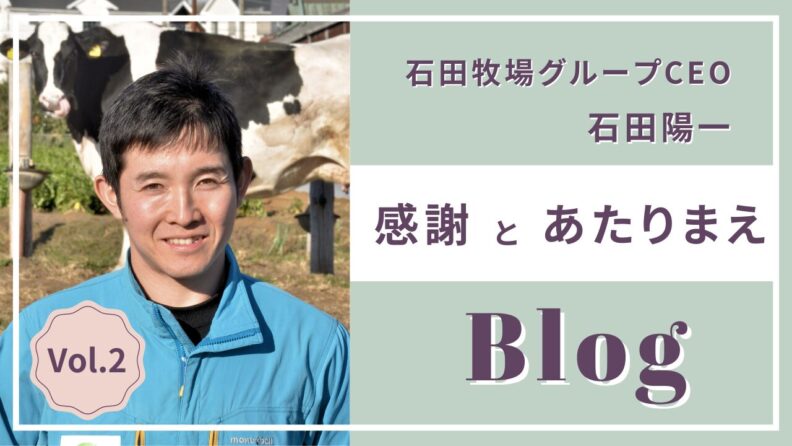『Dairy Japan』2024年11月号p.42「ルポ2」より
2021年に新設した搾乳ロボット牛舎で経産牛130頭を管理する有限会社葛巻千葉牧場。過去の経験を活かした蹄病の低減に向けた取り組みや施設・設備を聞きました。
削蹄師から酪農家に
岩手県葛巻町の標高約1000mに位置する葛巻千葉牧場。代表取締役の千葉博英さん(48歳)は、農業大学校を卒業後、スイスへ留学し酪農を学びました。帰国後は21歳から12年間削蹄師として働きながら、実家の牧場でも作業をこなす日々を送りました。「削蹄師と酪農家の両方を経験する中で、さまざまな牧場の良いところを学び、自分の牧場に取り入れることができました」と振り返ります。
当時は80頭のフリーストール牛舎でしたが、各地の牧場を見ていくうちに「将来はロボットで搾乳したい」と考えるようになりました。省力化だけでなく、「牛も人も自然体でいられる経営」を目指し、2021年にロボット搾乳を導入しました。現在は、搾乳ロボットに適さない牛やフレッシュ牛、乾乳牛を既存牛舎で管理しています。

牛舎設計のこだわり
「牛も人間も自然体でいられる酪農経営」を理念に掲げる同牧場は、蹄の健康にこだわり、新築牛舎には蹄病低減のための工夫を取り入れています。
千葉さんは「牛本来の生活を阻害しないよう、フリーカウトラフィックを採用した」と話します。これにより牛の行動が自然になり、ストレスが軽減。疾病予防や乳量向上にもつながっています。また、既存牛舎ではコンクリート通路に溝切りを施していましたが、発情牛の滑走事故が見られたため、新築牛舎ではBIORET CORP社のゴム製通路マットを導入しました。このマットには規則的な溝があり、尿は溝に落ち、糞は専用のバーンスクレーパーで掻き出される仕組みです。これにより通路が清潔に保たれ、滑走事故や皮膚炎が減少。さらに、蹄への負担が軽減され、白帯病の発症も激減しました。


また、搾乳ロボットを縦列に配置することで、牛の動線をスムーズにし、作業の効率化と衛生管理の向上を図っています。さらに、自動蹄浴槽を設置することで、日常的に蹄のケアを行なえる環境を整えました。元削蹄師としての経験が生かされた牛舎設計となっています。

放牧で脚を強化
同牧場では5月から10月末には放牧を取り入れています。千葉さんは「土の上を歩かせたい」と考え、自由に歩くことで牛の足腰が強くなり、運動量が増えて代謝が向上すると話します。この取り組みにより、分娩事故の抑制にもつながっています。
また、飼料設計にもこだわり、蛋白含量が過剰にならないよう調整。蛋白過剰による蹄葉炎などのリスクを抑えています。「削蹄師の経験があるからこそ、牛の症状を見て飼養管理や施設を改善できる」と千葉さんは語ります。
モニタリングの重要性
「どれだけ対策をしても蹄病がゼロになることはない」と千葉さん。蹄病の疑いがある牛には早期対応を徹底し、「重症化すると歩けなくなり廃用にせざるを得ない。異変に早く気づくことが重要」と強調します。
日々の観察に加え、地元普及員による定期モニタリングも実施。第三者の視点を取り入れることで見落としを防ぎ、蹄病の抑制につなげています。「複数の目でチェックすることが予防の鍵」と千葉さんは語ります。

タイミングの試行錯誤
今後の課題として、千葉さんは「通路マットのバーンスクレーパーの稼働タイミング」を挙げます。現在、スクレーパーで押し出された糞尿を牛が踏んでしまい、肢蹄が汚れることがあるためです。
この状況を改善するため、地元普及員と協力しながら牛群の行動を詳しくモニタリング。エサ押しロボットの稼働タイミングとスクレーパーの動作を調整し、牛が糞尿を踏みにくい環境を作る試行錯誤を続けています。蹄を清潔に保つことで、さらなる蹄病の低減を目指しています。
この記事が面白かったらシェアしてください!
↓ ↓ ↓
PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa
DairyJapan編集部。
1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。
趣味はサッカー観戦。
取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。
皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。