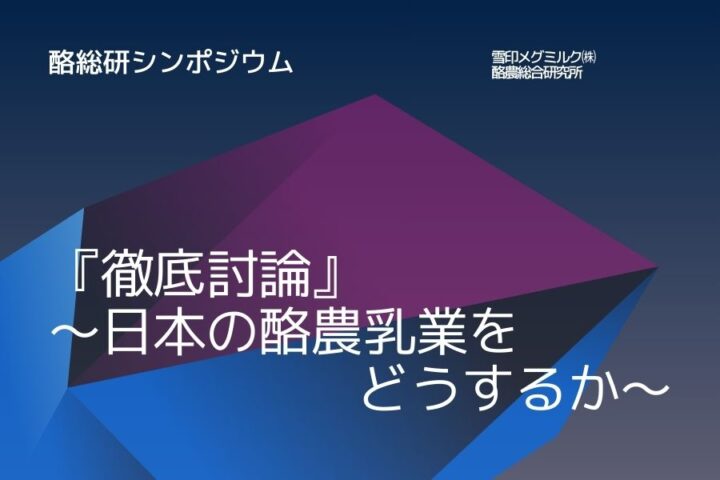こんにちは! ファームエンジンのラジオ配信で、アメリカ視察の話題から「繊維量」「NDF消化率」「飼料設計」について質問が寄せられました。内容がとても濃かったので、ポイントを整理してお届けします。ぜひご覧ください!
INDEX ➖
視察先の農場は“カウコンフォート”と“消化”が軸
今回訪れたのは、快適性(カウコンフォート)と繁殖性のレベルがとても高い農場。
そこでは NDFの消化 を何より重視していて、
30 時間 NDF消化率(NDFD30)の目標は 60%以上。
今年の日本のサンプルが 59%まで来ていて、あと少し、という話から議論が広がりました。
質問① 繊維量55%以上でも乳量はどこまで出るのか?
質問は「繊維量(NDF)55%以上で、どれくらい乳量が出るの?」というもの。
訪問した農場では、
・繊維量:58%前後(後期泌乳群)
・搾乳:3回搾乳(パーラー)
・乳量:45kg前後/日
・乳脂:4.2%程度(記憶ベース)
粗飼料が高めでも、メンテナンスできる穀物・副産物をうまく組み合わせて ME/MP を調整していました。
アメリカは「手持ちのカードでどう組むか」という文化が強く、
副産物原料を活用してコストを抑えつつバランスを取るのが一般的です。
質問②「番手が進むと消化率は落ちるのか?」への答え
日本では「2番草は消化率が落ちる」という経験則が強いですが、視察先では少し見解が違いました。
視察先の牧場では、
1番・2番・3番・4番の NDFD30 がすべて50%超。
番手による“明確な劣化”はあまり見られませんでした。
理由ははっきりしていて、
・刈り取り周期が早い(多刈り体系)
・刈り遅れない
・成熟ステージの差が小さい
つまり「番手より管理」。
日本の2番草が消化率で落ちるのは、
作業体系やスラリー散布のタイミング、とくに“刈り遅れ”の影響が大きいという話です。
質問③「DMI は設計通りに食べるのか?」という本質的な疑問
これが今回いちばん深いポイントでした。
多くの人が
「期待乳量→必要DMI→飼料設計」
という“逆算スタート”をしてしまう。
しかし、正しい順番は逆で、
現実の DMI(食べている量)こそがスタート地点。
・指示乳量は“結果”であり、
・設計は“今食べている量(DMI)”を基準に行う。
現場でズレが起きる最大の理由は、
“期待乳量から逆算した DMI”を牛が食べていないこと。
現実を基準にしないと、ME/MP も、乳量予測もぶれていきます。
追加情報:道東で NDFD30=69% の草が収穫された例も
視聴者からの情報提供では、
北海道・道東で NDFD30=69% のチモシー+白クローバーが今年収穫されたとのこと。
条件が整えば、安定して 3番草まで高品質を狙える という現場感も示されました。
これからの焦点:粗飼料体系の“再設計”
話の最後では、
・刈り取り体系
・在庫
・作業性
・コスト
をもう一度見直し、最適解を探りたいというところに。
最近は、ファームエンジンのライブ配信や個人の発信にも質問が多く、
コメントをきっかけにした“より深い議論”が広がっています。
こうした質問は今後もラジオで取り上げていく予定です。』皆さんからのご質問や話してほしいテーマのリクエストなどありましたらぜひお寄せください!
PROFILE/ 筆者プロフィール

大塚 優磨Otsuka Yuma
株式会社FarmEnJine代表。
「酪農業界にエンジンをかける」をモットーに、栄養・繁殖それぞれの専門的視点での酪農経営の課題の洗い出しや、酪農経営のゴール設定、など、「本当に酪農家を豊かにする」ためのサポートを行なう。
スタートアップの企業につき、Youtubeで酪農に役立つ情報を公開中