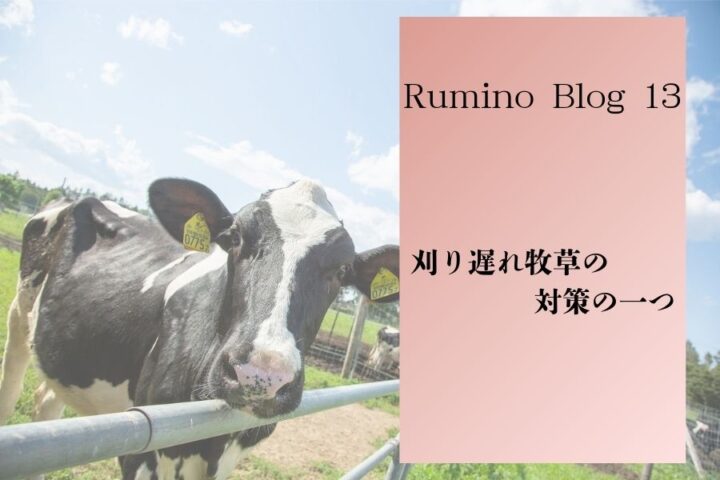Dairy Japan2025年9月号より
「どんな牛を残すべきか?」「その牛の能力をどう引き出すか?」――これらの問いに徹底的に向き合っているのが、北海道江別市の㈱Kalm角山。本特集ではその裏側と同社の方向性について取材しました。

㈱Kalm角山は搾乳牛550頭、未経産牛450頭を飼養し、全頭を8台の搾乳ロボットで管理。目標出荷乳量6424tという目標を掲げ、牛群改良はその達成に向けた重要な要素と位置づけています。
改良の方向性は……
同社では牛群改良において「客観的な数値に基づく判断」を重視。「改良した牛を戦力にできるかは、日々の管理次第」という方針です。創業は約10年前。5軒の酪農家が集まりスタートした当初は、牛のタイプや体型がバラバラでした。そこで、まずは搾乳ロボットに適した「コンパクトで足腰の強い牛」へと方向性を定め、次の段階では「疾病に強い長命な牛」、そして現在は「搾乳スピード」も重視する改良形質としています。


ゲノムとメイティングで「残すべき牛」を選ぶ
同社の交配計画では、ゲノム検査と、㈱野澤組が提供する「Optimate」などのメイティングプログラムを活用。感覚に頼らず、“残したい牛”ではなく“残すべき牛”を科学的根拠に基づいて選ぶ体制を整えています。
また、種雄牛の選定では「確実性」を重視し、改良速度よりも遺伝評価が安定したプルーブンサイヤを優先するという方針も特徴です。これらの方針管理は、統括マネージャーの山崎潤さんと受精を担当している㈱デーリィリプロテックがこまめに連携をとりながら進めています。
発情発見・妊娠確認も「見える化」
授精業務は㈱デーリィリプロテックが担当。U-motion(デザミス㈱)と、乳中プロジェステロン自動測定装置ハードナビゲーター(デラバル㈱)による二重チェック体制で、発情発見と妊娠確認の精度を高めています。
結果として、平均授精回数1.8回、平均空胎日数122日という好成績を実現。月ごとのホルスタイン雌の確保頭数を逆算し、必要な授精計画を立てている点も大きなポイントです。

生まれた子牛を確実に生かす
繁殖計画の中で、ホルスタイン雌以外は主にF1生産を目的とした和牛精液を使用しています。しかも、低価格な精液が中心ながらも高い市場価格で販売に繋げています。
高品質なF1子牛を出荷できるのは、「乾乳期管理」と「哺育管理」の徹底があるからです。
・乾乳舎の過密解消と分娩管理の強化
・哺乳器具の衛生管理やハッチの洗浄消毒
・生後10日までの下痢予防の石灰撒き
などを中心に「確実に生ませる。生まれたら確実に生かす」管理を徹底しています。こうした取り組みが、死産率3~5%、哺乳期の除籍率1~2%という低い数値につながっています。


まとめ:改良の先にある“舞台づくり”
㈱Kalm角山が牛群改良において最も重視するのは、「能力を発揮できる舞台(管理環境)」を整えること。改良はゴールではなく、その能力を引き出すための“手段”です。
川口谷社長や山崎潤統括マネージャーを中心に、すべてのスタッフが目標出荷乳量を常に意識しながら、個体ごとのデータに基づいて管理・改善を続けています。
日々の積み重ねが、やがて理想の牛群へと繋がっていく――。数値と管理の制度をさらに高めながら、㈱Kalm角山は止まることなく次のステップへと進み続けます。

PROFILE/ 筆者プロフィール

前田 真之介Shinnosuke Maeda
Dairy Japan編集部・北海道駐在。北海道内の魅力的な人・場所・牛・取り組みを求めて取材し、皆さんが前向きになれる情報共有をするべく活動しています。
取材の道中に美味しいアイスと絶景を探すのが好きです。
趣味はものづくりと外遊び。