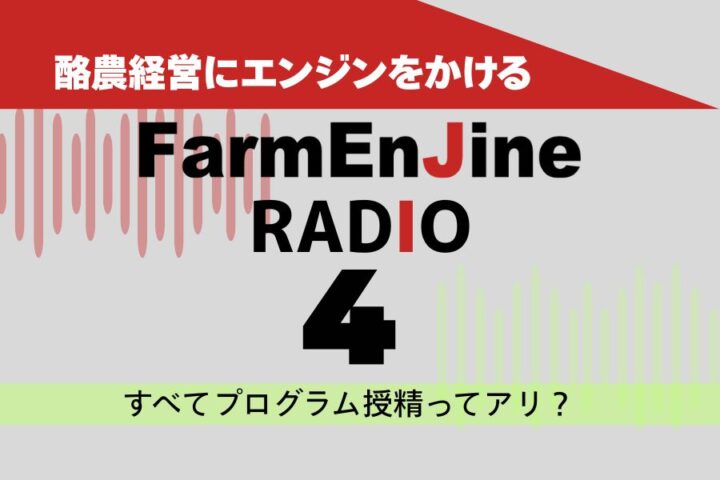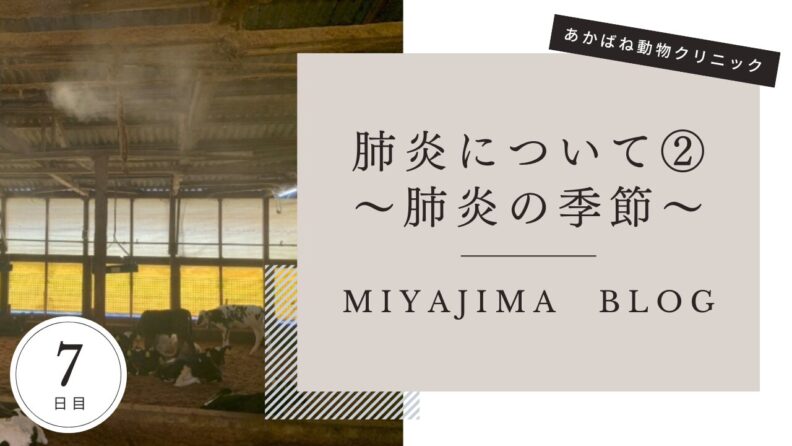子牛のお話をしている間に、北海道にも猛暑が来ましたので、暑熱対策に関して私の取り組みをご紹介しました。間が空いてしまいましたが、子牛、特に離乳までのお話をします。
前回に引き続き、私が伝えたい重要なことは、分娩前の母牛、胎子に対して良い管理をして「元気で強い子牛」が生まれてくることです。そのうえで適切な初乳給与をすることで「元気で強い子牛」に《微生物》の働きが加わり、さらに健康にしていくイメージです。すると哺乳管理、飼料管理が、計画通りに進められるので、スムーズな離乳につながっています。

そして、スムーズな離乳に向けては「水を飲み、スターター、草を食べ、ゆっくり寝る」ことを早期に習慣化できるかが重要です。
早期の習慣化が「先の管理」を楽にする
早期に固形飼料と水に馴れることで、ルーメンが十分に発達し、離乳時のストレスや成長の停滞なく、スムーズに育成牛の食生活へ移行できます。生涯にわたる生産性は、この哺育期の成長に大きく左右されるとよく耳にします。
順調に発育することで、育成牛は早くに繁殖可能な体になります。私の農場では、早期に授精し、初産分娩月齢は20カ月程度で迎えています。
私の作業上の経験ですが。決まった時間にエサを食べ、水を飲み、休むというリズムができると、牛は落ち着いて行動するようになります。これにより、給飼や清掃、健康チェックといった日々の管理作業が楽になり、管理者自身のストレスも軽減されます。
このように、哺育初期の手間を惜しまず、仔牛に良い習慣をつけさせることが、結果的に将来の管理を大幅に楽にし、経営全体の安定にも繋がる、非常に重要な投資になると考えます。
仔牛のスターターの一般的な給与例です。
1週目 100g
2週目 200g
3週目 400g
4週目 600g
5週目 800g
6週目 1.0㎏
2カ月(8~9週目)1.5㎏~2.0㎏
個体差や飼育環境に応じて調整が必要です。
水本牧場でのスムーズな離乳プログラム
うちでは「元気で強い子牛」を生ませているので、子牛達は哺乳以外で暇な時間があります。暇な時間があると周囲を散策しはじめ、いろいろなところを舐めたり、かじったりする行動を取ります。
なので、その行動を利用して、水、スターター、草に興味を持たせます。そして、舐める、かじるの延長が、飲む、食べるになります。だいたい生後2〜3日目から、給与し始めます。
草は、最初は栄養というよりも食べる習慣をつけてもらうのが目的となるので、食べやすいような、細くて柔らかい草を与えています。硬くて太い草だと、まだ未発達の子牛の臓器を傷つける恐れがあるので注意が必要です。うちでは、ハッチの敷料も食べても良い乾燥ロールを使っています。
スターターはカップで計って給与し、完食が続けば増量していきます。減乳法を使い、スターターが喰い込めるようにしています。スターターを朝夕で1kgずつ、合計2kgの完食が続いたら、次に配合を混ぜて朝夕でスターター1kg、配合0.5kgずつ給与します。合計3kgの完食が続いたら、今度はスターターも配合に変えていきます。

離乳の目安は60日で、そのときに配合を朝夕1.5kgずつの合計3kg完食を目指します。子牛によっては、離乳時にまだスターターが配合に完全には切り替わっていないときもあります。哺乳時からスターターから配合に切り替えるのは、哺育期から育成期にスムーズに移行するためです。環境が変わるときにエサまで変わってしまうと、子牛にはかなりのストレスがかかります。その時に喰い止まりが起きないための対策です。
余談ですが、哺育期の飼養管理は、より良い牛達を作ることを常に考えている、妻の『愛情』で成り立っています。『愛情』があるからこその、「観察力」、「行動力」、「技術力」だと思います。
基本的な飼養管理はありますが、結局はそのときの子牛によって対応はさまざまです。なので、子牛の管理はとくに「観察力」が重要です。その上での「行動力」、「技術力」が必要になります。
子牛の飼養管理は、まずはより良い牛達を育てようとする気持ちが大切だと思います。
次回は、離乳~3カ月までの管理です。